注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
「ISO認証」誌の中岡社長![]() のゴーサインがでたことを受け、増子(子)が増子(父)に伝えると、増子(父)は契約審査員をしている認証会社に、ISO雑誌にコラムを書くことの了解を取った。
のゴーサインがでたことを受け、増子(子)が増子(父)に伝えると、増子(父)は契約審査員をしている認証会社に、ISO雑誌にコラムを書くことの了解を取った。
認証機関の役員は、守秘に当たること以外は自由に書いて良いと了承したが、逆に認証機関の宣伝にもなるからと、働いている認証機関名を明示することを求めた。契約審査員と書くとなんだから、そこは審査員とするようにという。
増子父のコラムが載った10月号は9月下旬に発行された。
内容は次のようなものだった。
|
ISO徒然草 その1「敵を知れ」 私は認証機関〇〇でISO9001とISO14001の審査員をしている。縁あって、私にISO認証誌のコラムを書く機会をいただいたので、誰もが知りたいこと、困っていることの対応を書いていきたい。 もちろんコラムの掲載が続けばなので、ぜひとも、面白かった、もっと読みたいと出版社にメールしてほしい。 既に多くの方々が、ISO認証とは何か、認証する流れ、ISO規格の解説、審査とはどんなものかなど、書籍やネットに書かれている。もう改めて書くこともないことがないようにも思える。 だが企業のISO担当者が困っていること、例えば審査員が語ることが理解できない、不適合を言われたが何が悪いか分からない、是正処置として何をしたら良いのか分からない、理想を言われても困る、ウチは大企業じゃないぞ、その他、困り果て途方に暮れている話を多々耳にする。 それでISO規格の理解やISO審査に苦労しているたくさんの人の、助けになるものを書きたいと思った。 今回は第1回目です。初回は審査とは何かを考えたい。 世の中のビジネスは、売り手と買い手がいて成り立つ。認証機関は審査というサービスの売り手(供給者)であり、買い手(依頼者)は認証を受けようとする会社だ。商取引において、売り手と買い手は対等である。 だが、現実の審査は審査側が上から目線だ。審査員も企業側も、審査を受ける方を対等な相手でなく、教えを乞う生徒とか取り調べを受ける被疑者のような感じを持っているのではないだろうか? まして、現時点、認証機関は売り手市場で、売り手の態度が大きい。 企業側はもっと自信を持たねばならない。商取引なのだから、不明点があれば相手に説明させてよく、納得できないなら同意せずに異議申し立てをすれば良く、不満があれば苦情を申立てれば良い 折り合いがつかなければ別の業者を当たるのも良い。その前に相見積もりは当然である。 納得できないがどこに言ったら良いかと迷うこともない。認証機関には苦情窓口はあるし(苦情窓口を明示しないとルール違反)、決着がつかなければ裁判をしてもよい。 お前は審査員の味方ではないのかとおっしゃるな。審査は敵か味方かの関係ではない。商取引は双方がWIN-WINの関係であるはずだ。 そういうことはISO審査のルールに決めてあるのだ。契約の双方がルールを知って守らなければ、まっとうな審査はあり得ない。 私の言うことを否定する審査員がいれば、いないとは思うが、認証機関や審査員登録機関に苦情を申し立てればよろしい。 審査員と会社は対等、 巷で聞く審査員や審査の問題を考える。 まず言葉使いである。難しいことは言わない、通常のビジネスと同様な言葉を使うべし。 審査員に対して普通のビジネス敬語を使えば十分である。同様に審査員も普通のビジネス敬語を使わねばならない。 社外の方を呼ぶには「さんつけ」だろう。聞くところでは「〇〇先生」と呼ばないと返事をしない審査員もいるらしい 買い物に来た大人の客に「坊主、何を買いに来た?」と言う店員はいないだろう。 取引先の営業マンが失礼な態度をとれば、先方の管理者に「お宅の営業マンが無礼きわまる。人を変えてくれ」と電話しておかしくない。 審査員が社長や工場長にタメ口をきくなら、認証機関に「お宅の審査員が無礼きわまる。人を変えてくれ」と電話しましょう 商取引では、お互いビジネス敬語で話すのは当たり前です。 名刺交換するときは、名詞を片手で出さない、片手で受け取らない。両手で渡し、両手で受け取る。
オープニングで経営者が挨拶しているとき、最前列で脚を組んでいた審査員もいましたね。 当たり前だなんて言わないで、そういう審査員ばかりを見てきたものですから・・・ オープニングミーティングで、「皆さんを指導する」とか「アドバイスをよく聞きなさい」なんて発言をする審査員もいる。これは非常に危険です。 会社にとってではなく、審査員にとってです。 ISO審査は、企業の手順と運用がISO規格を満たしているか・いないかを点検するのが目的で、悪いところを直すとか、現状をより良くするためではありません。 審査のルールでは、指導とかアドバイスを禁じています。ひょっとすると資格員の資格が取り消しになるかもしれません。 またオープニングミーティングや審査の過程で、他社の状況や不適合の内容などを語ることは守秘義務に反します 審査契約書に審査員の守秘義務が書いてあるはずです。それって契約違反ですね。 ではISO審査では指導を受けられないのかと思うでしょう。その通り、審査では改善の指導も、是正処置を教えることもNGです。審査とは善し悪しの判定だけ、コンサルや講習ではありません。 となると「会社を良くする審査をする」なんて語る認証機関は何をするのでしょう? 考えても分かりませんから、次に行きましょう。 審査の結果は、審査を受けた組織がISOMS規格を満たしているか、満たしていないかを判定することです。 満たしていないことを不適合と言います。不適合とは、規格要求に適合していないことですね。不適合だと言い切るには、証拠と根拠が必要です。 注:ISOMS規格とはISOのマネジメントシステム規格のこと。マネジメントシステムと自称したのはISO14001が嚆矢です。ISO9001は2000年改定までMS規格ではありませんでした。
裁判には「罪刑法定主義(憲法31条)」という原則があります。それは有罪とするには法律で「これをしてはいけないと決めていなければならない」ことです。 注:この物語は1997年時点ですから、ISO14001:1996を基にしています。
所見報告書に「4.4.5文書管理に反しています」なんてあれば、審査料金を払うに値しません。何を語っているのか分かりませんから、差し戻しですね。 |
押田から「最初は読者のつかみをしっかりと」と言われたが、増子(子)も増子(父)もそんなに器用じゃない。とりあえず思うことを書いてみた。
押田編集長は、一読して審査員から苦情が来るのではないかと心配する。
増子(父)は、書いたことはすべてルールにあることだ。だからこれに反論することはルールを知らない人で、もめても大丈夫と言う。
押田![]() はそれを受けて、増子(父)の書いたものをそのままアップすることにした。
はそれを受けて、増子(父)の書いたものをそのままアップすることにした。
一応、コラムの末尾に「このコラムの文責は著者にあります。本誌は正否を確認していません」と一文を追加した。
印刷したものを発行日前に、増子(子)が増子(父)に持ってきた。
![]() 「ワシの文は読むまでもない。編集長が今回から企業の人向けに舵を切ると言っていたが、内容は変わったのか?」
「ワシの文は読むまでもない。編集長が今回から企業の人向けに舵を切ると言っていたが、内容は変わったのか?」
![]() 「舵を切ると言っても一挙に全面変更できるわけじゃない。認証機関の偉いさんの話とか、新しいISOMS規格の解説など、連載物は変わらないよ。
「舵を切ると言っても一挙に全面変更できるわけじゃない。認証機関の偉いさんの話とか、新しいISOMS規格の解説など、連載物は変わらないよ。
もうだいぶ前になるけど、〇〇業界のISO研究会のメンバーの取材というか飲み会があったことは話したよね。そのときの議論を編集して載せている。お父さんの後ろ10ページくらいに載っている。
今月号の新機軸はその二つだけかな」
![]() 「おっ、これだな。
「おっ、これだな。
どれどれ・・・・」
・
・
・
・
20分ほど読んで、増子(父)は口を開いた。
![]() 「以前、お前に見せてもらった速記録よりも、冗長がなくなり要点がはっきりした。
「以前、お前に見せてもらった速記録よりも、冗長がなくなり要点がはっきりした。
研究会の中心人物は佐川という人のようだ。この佐川という人に会ったのか?」
![]() 「ああ、この取材のとき一度だけ会って話をした。何でも知っているっていう自信過剰な人だったな」
「ああ、この取材のとき一度だけ会って話をした。何でも知っているっていう自信過剰な人だったな」
![]() 「話していることに間違いはない。
「話していることに間違いはない。
この人はISO9001から数えると、百件以上コンサルをしているそうだ。それほどの経験があるなら、語ることはウソではあるまい。
会って話をしたいものだ」
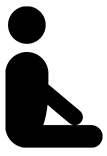 |
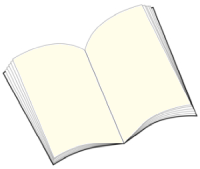
| 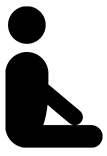 |
![]() 「編集長が、ゆくゆくは『研究会VS審査員』特集もしたいと言っていたから、そのうち願いは叶うよ」
「編集長が、ゆくゆくは『研究会VS審査員』特集もしたいと言っていたから、そのうち願いは叶うよ」
![]() 「それは楽しみだ。審査員冥利に尽きるとは、こういう奴と相まみえることだろうなあ。
「それは楽しみだ。審査員冥利に尽きるとは、こういう奴と相まみえることだろうなあ。
編集長に言ってくれ。その『研究会VS審査員』特集を次号くらいでやって欲しいって」
![]() 「お父さん、そう簡単にはいかないよ。まずおとうさんのコラムが好評であることと、研究会の記事も好評でないと。
「お父さん、そう簡単にはいかないよ。まずおとうさんのコラムが好評であることと、研究会の記事も好評でないと。
なにしろウチの雑誌もビジネスだから、好評でないと即打ち切りだよ」
![]() 「そりゃ、そうだ。ワシの載っている10月号が売れて、読者から面白いから続けてという声が来ないとダメか、なんとか続きますように。
「そりゃ、そうだ。ワシの載っている10月号が売れて、読者から面白いから続けてという声が来ないとダメか、なんとか続きますように。
そうだ今度、認証機関に行ったら、周りの人に薦めておくよ」
![]() 「ごり押しすると逆効果だよ」
「ごり押しすると逆効果だよ」
![]() 本日のお詫び
本日のお詫び
本日は5,000字しかありません。「タイムスリップISO物語」では最短です。
実を申しまして、私の周辺がドタバタしており身が入りません。
今回はお許しのほどを・・・・
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
異議と苦情はISO認証においては意味が違う。いずれも一般語としての異議とか苦情ではなく、正式なルートによる申立てを意味する。 現在はISO17021によるが、以前はguide62とか66だったと思う(定かではない)。 ISO17021-1:2015では大体次のようだ。 異議とは審査を受ける組織が、不適切と考えることについて問題提起をし、変更を求めること。 例:審査メンバーについて変更を求める、不適合について反論する等 苦情とはISO認証を利用する者ならだれでも申し立てできる。内容は審査や認証のパフォーマンスとある。 例:あの会社は品質が悪いのになぜISO9001が認証できるのか? 認証機関は異議や苦情を受け付ける窓口(メアド・電話番号など)を公表しなければならない。 | |
| 注2 |
よく言われることで、都市伝説かと思っていた。私が引退してからだから2015年頃、このウェブサイトの読者から〇〇さんが審査に来た。先生と呼ばないと振り向かなかったという。 アイソス誌などでよく顔写真を見かける審査員だった。見た目と中身は違うんだと感動した。 | |
| 注3 |
 これは何度も見かけた。あるとき「坊や」と呼ばれたのは30歳くらいの技術者だった。ご本人は坊やとは自覚しておらず、何度も呼びかけられても自分とは考えなかった。周りの人が袖を引っ張って「審査員が質問したいそうだ」と教えてやった。
これは何度も見かけた。あるとき「坊や」と呼ばれたのは30歳くらいの技術者だった。ご本人は坊やとは自覚しておらず、何度も呼びかけられても自分とは考えなかった。周りの人が袖を引っ張って「審査員が質問したいそうだ」と教えてやった。最後まで自分が坊やとは自覚しなかったようだ(笑) 「坊主」というのも何度か聞いた。そういう言葉使いの審査員は、ビジネスの世界では不向きだろう。 | |
| 注4 |
社長ではなかったが、東証一部(当時)の役員にため口を叩いた審査員がいた。役員本人は気にしなかったようだが、周りの人は審査員がおかしいのではないかと翌年は(以下略) | |
| 注5 |
他社の事例を語る審査員は多かった。社名を言う人も隠す人もいたが、隠しても業種とか所在地などからだいたいは分かった。 自分達の工場も他所に行って話しているのだろうなと思った。怒るまではないが、おかしいと思った。 | |
| 注6 |
厳密に言えば、提供したほうは不正競争防止法違反、受け取った方は背任などの罪に問われる。 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |

 審査が終わりました。クロージングミーティングで不適合を出されたらしっかりと根拠と証拠を確認しましょう。
審査が終わりました。クロージングミーティングで不適合を出されたらしっかりと根拠と証拠を確認しましょう。