注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
1997年10月、業界のISO研究会の定例日である。
今日は珍しくほとんどが出席している。理由はある。
吉本 |  須藤 須藤 | |||
| 金子 |  佐川 佐川 |
|||
| 田中 |  山口 山口 |
|||
| 高橋 |  鈴木 鈴木 |
|||
| 小林 | ||||
![]() 「みんな知っていると思うけど、8月に『ISO認証誌』の取材といか飲み会があったよね(第90話)。そのときの論議が10月号に載っている」
「みんな知っていると思うけど、8月に『ISO認証誌』の取材といか飲み会があったよね(第90話)。そのときの論議が10月号に載っている」
田中はテーブルの右と左に一冊ずつ『ISO認証』の10月号を回す。
![]() 「あら、私の発言も載っているわ♥」
「あら、私の発言も載っているわ♥」
![]() 「話し合ったことを見ると、愚痴ばっかりだ。しかも問題は無関係な押田さんに責任があるような言い方だ。反省、反省」
「話し合ったことを見ると、愚痴ばっかりだ。しかも問題は無関係な押田さんに責任があるような言い方だ。反省、反省」
![]() 「でも押田さんは業界誌の記者なのだから、そういった問題を取り上げる責任があるよね。今まで雑誌に取り上げていなかったのだから、それは押田さんが責められても仕方ないよ」
「でも押田さんは業界誌の記者なのだから、そういった問題を取り上げる責任があるよね。今まで雑誌に取り上げていなかったのだから、それは押田さんが責められても仕方ないよ」
![]() 「まあ、そういうこともあって、我々に取材に来て記事にしたことでしょう。
「まあ、そういうこともあって、我々に取材に来て記事にしたことでしょう。
PDCAが回っているならいいじゃないか」
![]() 「その通りだよ。ア〇〇ス誌は審査員や認証機関の方を向いているね。審査のトラブルなどを取り上げたことがない。ア〇〇ス誌だって審査の問題を認識しているはずだから、間違えている規格解釈とか審査のミスなどを取り上げてほしいよ。
「その通りだよ。ア〇〇ス誌は審査員や認証機関の方を向いているね。審査のトラブルなどを取り上げたことがない。ア〇〇ス誌だって審査の問題を認識しているはずだから、間違えている規格解釈とか審査のミスなどを取り上げてほしいよ。
審査を受ける側と言っても、〇〇フォーラムのような規格マニア相手じゃなく、現実の審査のトラブルを把握して、問題提起しなくちゃジャーナリズムじゃないよ」
![]() 「鈴木さんの言うように、〇〇フォーラムのような神学論争じゃなくて、現実が見えない審査員をどう説得するとか、審査員を替える方法を知りたいんだ」
「鈴木さんの言うように、〇〇フォーラムのような神学論争じゃなくて、現実が見えない審査員をどう説得するとか、審査員を替える方法を知りたいんだ」
![]() 「それにしてもあのときは酒も入っていて、私が聞いていても支離滅裂だったが、良くまとめたというか作文したものだ」
「それにしてもあのときは酒も入っていて、私が聞いていても支離滅裂だったが、良くまとめたというか作文したものだ」
![]() 「押田さんに付いてきた増子とやらが、ワープロ起こしして、上手くまとめたんだろう。あいつも見た目よりはましなのかもしれない」
「押田さんに付いてきた増子とやらが、ワープロ起こしして、上手くまとめたんだろう。あいつも見た目よりはましなのかもしれない」
![]() 「オイオイ、見てみろ、我々の後ろに『ISO徒然草』なんていう、新しい連載が載っているよ。それを書いている審査員の名が増子とある。ひょっとして、増子記者本人か、奴のオヤジじゃないのか?」
「オイオイ、見てみろ、我々の後ろに『ISO徒然草』なんていう、新しい連載が載っているよ。それを書いている審査員の名が増子とある。ひょっとして、増子記者本人か、奴のオヤジじゃないのか?」
![]() 「増子の年齢では審査員にはなれないだろう。本人ということはないな」
「増子の年齢では審査員にはなれないだろう。本人ということはないな」
注:審査員になる要件では高卒5年、大卒4年以上の実務経験が必要、そのうち2年は環境マネジメント分野の業務となっている。
![]() 「じゃ、オヤジかよ?」
「じゃ、オヤジかよ?」
![]() 「そう言えば、増子記者は審査員を批判する言葉に、ひたすら反論していたね。オヤジが審査員だから、あんな態度だったのかもしれん」
「そう言えば、増子記者は審査員を批判する言葉に、ひたすら反論していたね。オヤジが審査員だから、あんな態度だったのかもしれん」
![]() 「そう言われると、そう思えるなあ〜」
「そう言われると、そう思えるなあ〜」
![]() 「なるほど、確かに顔も似ている。審査員にコラムを書いてもらおうと考えたが、知り合いがいないから縁故を頼ったということか?」
「なるほど、確かに顔も似ている。審査員にコラムを書いてもらおうと考えたが、知り合いがいないから縁故を頼ったということか?」
 |  |
![]() 「ひょっとして書いているのは増子父でなく、増子息子かもしれないよ。記者になるくらいだから、文才はあるだろう」
「ひょっとして書いているのは増子父でなく、増子息子かもしれないよ。記者になるくらいだから、文才はあるだろう」
![]() 「待て、待て、そもそも親子かどうか定かでないよ、アハハハ」
「待て、待て、そもそも親子かどうか定かでないよ、アハハハ」
![]() 「ええと話を戻します。
「ええと話を戻します。
押田さんから、この記事を掲載する前に現行の確認依頼がありました。幹事会で山口さんと金子さんと中村さんそして私で、内容を確認して問題ないと判断しました。
押田さんからは取材のお礼として・・・」
![]() 「2万円位かな? もっとか?」
「2万円位かな? もっとか?」
![]() 「オイオイ、有名人じゃあるまいし、3,000円ですよ。取材を受けたのは業界団体ではなく企業でISO14001担当している人たちとしてだから、このお金は我々のものです。
「オイオイ、有名人じゃあるまいし、3,000円ですよ。取材を受けたのは業界団体ではなく企業でISO14001担当している人たちとしてだから、このお金は我々のものです。
そうは言っても、一人当たり300円ではしょうがないから、次回飲み会に拠出することにしますね」
![]() 「異議ナーシ」
「異議ナーシ」
 |
|
ないのよよよ |
とはいえ顔を出さないわけにもいかず、この場にいるのも針の筵かもしれない。
![]() 「じゃあ、雑誌掲載のことはオシマイにします。
「じゃあ、雑誌掲載のことはオシマイにします。
次は毎度のことですが、このひと月の審査で起きた問題報告です」
![]() 「私の企業グループの状況です。
「私の企業グループの状況です。
以前、佐川さんが話をされた審査トラブルがすべて現れましたね。流石予言者!
具体的には、規格の言葉が入っていない。特に環境方針では『枠組み』、『継続的改善』ですね。それを盛り込めと言われています。
言われるとおりにすると、環境方針と言うより規格文言そのままですよ、アハハ。
環境マネジメントプログラムでは目的と目標の2個が必要と言われて、ウチは1枚しか作ってなかったから、不適合になっています。
環境側面の決定は客観的でなければならないとして、スコアリング法以外は実質ダメです。
『自覚』とは著しい環境側面に関わらない人に行う教育だと、審査員は語っていました。規格を読んでないんじゃないですかね。
『緊急事態』とは一定以上の損害とか危険のあるものに限定しろと言う
しかしね、審査員は『君たちの負担を減らしてあげようとしたのだが』と言ってました。アタオカですかね?
内部監査は環境マネジメント構築、実行部門からはずれた部門で、責任・権限が独立していないとならず、環境部門や管理責任者でない者が組織すること、これは不適合になりました。
いやあどこが悪いのかワケワカランです。そもそも規格に書いてないと思います」
![]() 「それはもうISO14001じゃなくて、その認証機関が作った規格じゃないの?」
「それはもうISO14001じゃなくて、その認証機関が作った規格じゃないの?」
![]() 「スコアリング法でないとダメとか、規格の言葉が入っていないから不適合というのが多いですね。
「スコアリング法でないとダメとか、規格の言葉が入っていないから不適合というのが多いですね。
あっ、私のところではマニュアルでもそうですが、会社の手順書、ウチでは会社規則と呼んでいますが、その中でも用語はISOの用語を用いろ、定義も合わせろと言われています」
![]() 「そうしないと不適合になりますか?」
「そうしないと不適合になりますか?」
![]() 「不適合ではないのですよ。気付きとか注意点とかいう名目になっています」
「不適合ではないのですよ。気付きとか注意点とかいう名目になっています」
![]() 「それはそのままで良いのか、改善しなければならないものなのですか?」
「それはそのままで良いのか、改善しなければならないものなのですか?」
![]() 「それが良く分からないのです。『次回までに対応してください』と言われているのです。困ります」
「それが良く分からないのです。『次回までに対応してください』と言われているのです。困ります」
![]() 「所見報告書に不適合と書いて無ければ無視すれば良いよ。
来年の出方を見たらどうでしょう。いちゃもん付けてくるならそこで反論する」
「所見報告書に不適合と書いて無ければ無視すれば良いよ。
来年の出方を見たらどうでしょう。いちゃもん付けてくるならそこで反論する」
![]() 「審査員個人の考えですか? 認証機関の統一見解ですか?」
「審査員個人の考えですか? 認証機関の統一見解ですか?」
![]() 「同じ認証機関からくる審査員は同じことを言うから、審査員のバラツキではなく、認証機関の方針のようだ」
「同じ認証機関からくる審査員は同じことを言うから、審査員のバラツキではなく、認証機関の方針のようだ」
![]() 「ちょっと毛色が違うものがあったので報告します。
「ちょっと毛色が違うものがあったので報告します。
内部監査で指摘事項に根拠として規格要求事項、それから証拠を明確に書いていたら、細かすぎると言われました。
それが不適合ですよ、不適合。信じられない」
注:21世紀も四半世紀過ぎた今では、『審査のたびに不適合があること』に驚くかもしれない。
20世紀はQMSでもEMSでも、審査のたびに指摘事項が2件から4件あるのは普通だった。中身はろくでもないことだったけどね。
当時、会社側では審査員もお土産がないと困るのだろうと諦めていた。
リアルのお土産を持って帰り、不適合を置き土産にしていくとは困ったことだ。
![]() 「その不適合の証拠と根拠はどう書いていましたか?」
「その不適合の証拠と根拠はどう書いていましたか?」
![]() 「不適合は項番だけ、つまり『4.5.4環境マネジメントシステム監査』と書いているだけです。どこが、どの規格要求に反しているか全然分かりません。
「不適合は項番だけ、つまり『4.5.4環境マネジメントシステム監査』と書いているだけです。どこが、どの規格要求に反しているか全然分かりません。
監査報告は経営層に出すものだから細かく書かないと言われました」
![]() 「そう言われると、そういう気もするなあ〜」
「そう言われると、そういう気もするなあ〜」
![]() 「須藤さんはどう対応したのですか?」
「須藤さんはどう対応したのですか?」
![]() 「不適合の根拠と証拠が分からないので、ウチの内部監査と同じくらい証拠と根拠をはっきり書いてくださいと言うと、面白くない顔をしていたが不適合は取り消しました」
「不適合の根拠と証拠が分からないので、ウチの内部監査と同じくらい証拠と根拠をはっきり書いてくださいと言うと、面白くない顔をしていたが不適合は取り消しました」
![]() 「不適合がなくなっちゃたの? うーーん、全くワケワカラン」
「不適合がなくなっちゃたの? うーーん、全くワケワカラン」
![]() 「ウチで困ったのは、法律を知らない審査員だな。
「ウチで困ったのは、法律を知らない審査員だな。
マニフェストを書いたこともないどころか、見たこともない審査員が言いたい放題言うのを、黙って聞いていた私をほめたいよ」
注:「自分で自分をほめたい」は前年1996年のアトランタオリンピックで、女子マラソン銅メダルを取った有森裕子の名言。この時期は普通に皆が使っていた。
![]() 「どんな問題があったのですか?」
「どんな問題があったのですか?」
![]() 「問題じゃないよ、審査員が問題だと言っただけさ。ナンセンスコールだった。
「問題じゃないよ、審査員が問題だと言っただけさ。ナンセンスコールだった。
中村 |
|
吉 本 |
![]() 「押印と書いてあれば、ハンコを押さなくちゃならないのでしょう?」
「押印と書いてあれば、ハンコを押さなくちゃならないのでしょう?」
![]() 「マニフェストは法律で記載事項が決めてあるのだけど、押印しろとはない
「マニフェストは法律で記載事項が決めてあるのだけど、押印しろとはない
帳票は行政が印刷して販売しているわけではなく、民間が営利事業として印刷して販売しているわけよ。だから市販されているマニフェスト票の記載事項は法を満たしているけれど、法で定めること以外の項目もある」
注:これは現実に何度もあった。私はその外資系の某認証機関に行って、偉いさんに「困ります、しっかり指導してください」と申し入れたことがある。
困る |
私は諦めて工場には、何もせずに翌年の審査で問題ないことを説明しろと言った。次回の審査の是正確認では揉めなかったようだ。
だが同じ指摘はそれ以降も出された。こんな認証機関に「とられた是正処置が再発防止になっていない」と言われたくない。
![]() 「それでハンコ押さなくても問題ないの?」
「それでハンコ押さなくても問題ないの?」
![]() 「法的に問題ない。
「法的に問題ない。
法令では『管理票の交付を担当した者の氏名』となっていて、押印はない。民間のマニフェスト票製造者がサービスで ㊞ と印刷したにすぎません
| 管理番号 | 交付担当者 |
![]() 「言われてみると、今はハンコが必要なものはどんどん減っているわね」
「言われてみると、今はハンコが必要なものはどんどん減っているわね」
・
・
・
・
![]() 「審査で出された不適合は、皆さんの見解では8割は問題ない、つまり不適合ではないという結果でした。
「審査で出された不適合は、皆さんの見解では8割は問題ない、つまり不適合ではないという結果でした。
対応ですが、基本的に不適合を出された会社の判断です。不適合撤回に支援してほしいなら、法律の調査とか他の認証機関の審査判定などの情報収集・提供の協力をしたいと思います。
正直言って、悪貨は良貨を駆逐すると言いますように、間違えた規格解釈がはびこると、他の認証機関に感染が拡大します。それがデファクトスタンダードになる恐れもあります。
ですからおかしな見解は、広まる前に叩き潰すのが好ましいのですが」
![]() 「不適合を出された会社の対応はどんな状況でしょうか?」
「不適合を出された会社の対応はどんな状況でしょうか?」
![]() 「私が相談を受けて、不適合を出された工場や関連会社と話をしまして、断固拒否したい工場は、私とそこの担当者が認証機関を訪問して不適合の取り消しを交渉しているところです」
「私が相談を受けて、不適合を出された工場や関連会社と話をしまして、断固拒否したい工場は、私とそこの担当者が認証機関を訪問して不適合の取り消しを交渉しているところです」
![]() 「全部のところが、不適合の撤回を望んでいるわけではないのですか?」
「全部のところが、不適合の撤回を望んでいるわけではないのですか?」
![]() 「そうですねえ〜、中には次回審査で復讐されたらたまらないから、言われた通りしておくというところもありますね」
「そうですねえ〜、中には次回審査で復讐されたらたまらないから、言われた通りしておくというところもありますね」
![]() 「確かに規格の言葉を入れろと言われた程度なら、言葉を追加したほうが楽だ……となりますね」
「確かに規格の言葉を入れろと言われた程度なら、言葉を追加したほうが楽だ……となりますね」
![]() 「でも方針なら、トップの書いたものに手を加えるというのは、それもまた問題ではないですか?
「でも方針なら、トップの書いたものに手を加えるというのは、それもまた問題ではないですか?
方針とは社長が心を込めて書いたものでしょう」
![]() 「そういう経験はウチにもあるよ。結局、上長次第だね。事なかれ主義だと直せとなるし、骨がある方だとフザケルナとなる」
「そういう経験はウチにもあるよ。結局、上長次第だね。事なかれ主義だと直せとなるし、骨がある方だとフザケルナとなる」
![]() 「フザケルナとなれば、認証機関に交渉するわけですか?」
「フザケルナとなれば、認証機関に交渉するわけですか?」
須藤はニヤニヤして返事をしなかった。
![]() 「マネジメントプログラムが二つないと不適合で面白いことがありました。
「マネジメントプログラムが二つないと不適合で面白いことがありました。
ウチの工場に審査に来た審査員が、それを不適合にしたのです。工場の担当者が納得せず、後日、彼と私が認証機関に苦情を言いに行きました。
しばし議論したのですが、先方は重大問題ではないからと不適合から削除しました。重大問題かどうかはこの際おいときます。
ところがそれから半月もしないで、同じ審査員が関連会社の審査に来て、そこでまたマネジメントプログラムがふたつないことを不適合にしたのです」
![]() 「そりゃ、また・・・気が付いたことだけ対策するのは処置だっけか? 同じ問題を起こさないようにするのが是正処置だよね」
「そりゃ、また・・・気が付いたことだけ対策するのは処置だっけか? 同じ問題を起こさないようにするのが是正処置だよね」
![]() 「そういう審査を見ていると、恣意的な判断だと怒りますね。
「そういう審査を見ていると、恣意的な判断だと怒りますね。
相手が強く出れば引っ込め、相手が弱気なら強く出る、人間の屑ですよ」
![]() 「人間の屑かどうかはともかく、審査員の屑ではあるだろうな〜
「人間の屑かどうかはともかく、審査員の屑ではあるだろうな〜
でも、そういうのをどうするか、我々は暴れん坊将軍とか水戸黄門じゃないからね。必殺仕事人と同じく、依頼を受けて行動するだけだ
![]() 「あれ、悪貨は良貨を駆逐すると言ったのは誰?」
「あれ、悪貨は良貨を駆逐すると言ったのは誰?」
![]() 「うーん、悪い審査が蔓延するのは困るし、そういうのは広まるのが早いのは確かだ。
「うーん、悪い審査が蔓延するのは困るし、そういうのは広まるのが早いのは確かだ。
でも、デタラメな審査でも言われた通り受け入れるところに、頼まれもしないのに助けに行く気はないね」
![]() 「悪貨の蔓延を、手をこまねいて見ているわけ?」
「悪貨の蔓延を、手をこまねいて見ているわけ?」
![]() 「我々はISO認証が天職じゃない。会社の仕事でたまたまISO認証と関わったに過ぎない。はっきり言ってISO認証制度がポシャっても困らないし気にしないよ」
「我々はISO認証が天職じゃない。会社の仕事でたまたまISO認証と関わったに過ぎない。はっきり言ってISO認証制度がポシャっても困らないし気にしないよ」
注:「天職」にもいろいろ意味があるが、ここでは『天から授かった仕事』と解してください。
![]() 「まあ、分かるけど、言われたことをそのままするようなことでは、ISO認証はダメになるよね。ゆくゆく自分の足元までダメになる気がする。蟻の穴から堤も崩れるですよ」
「まあ、分かるけど、言われたことをそのままするようなことでは、ISO認証はダメになるよね。ゆくゆく自分の足元までダメになる気がする。蟻の穴から堤も崩れるですよ」
![]() 「堤防が崩れても被害を受けるのは我々じゃなくて、ISO第三者認証制度でしょう。我々は痛くも痒くもないよ」
「堤防が崩れても被害を受けるのは我々じゃなくて、ISO第三者認証制度でしょう。我々は痛くも痒くもないよ」
![]() 「金子さんの言いたいことは良く分かる。だけど我々はスーパーヒーローじゃない。できる範囲に手を差し出すだけだ。
「金子さんの言いたいことは良く分かる。だけど我々はスーパーヒーローじゃない。できる範囲に手を差し出すだけだ。
田中さんの言う通り、第三者認証制度がなくなっても困らない。私が気にしているのは、現在の第三者認証制度で迷惑を受けないことだ」
![]() 「まさしく、佐川さんのおっしゃる通りですね。
「まさしく、佐川さんのおっしゃる通りですね。
天は自ら助くる者を助けるしかできないよ」
![]() 「そうかもしれない。
「そうかもしれない。
自分の会社の仕組みが悪くなるのは止めたいね」
![]() 「そういう意思のあるところが、助けを求めるなら支援するよ。そういうこと」
「そういう意思のあるところが、助けを求めるなら支援するよ。そういうこと」
・
・
・
・
結局、研究会として何かを推進するということまで話は進まなかった。参加メンバーが指摘事項を撤回させようとか、審査の問題を改善しようとするときは、研究会が対策に協力することは決まった。
世の中でおかしな審査が流行ろうと、それを徹底的に阻止するには研究会に力がない。
自分たちの手が届くところしか救えない。
それにしてもまともな解釈をしない審査員の多いこと、そしてユニークな解釈を考え付くことに感心してしまう。
終わりなく登場するおかしな規格解釈を論破する、このモグラ叩きは終わりがないのだろうか?
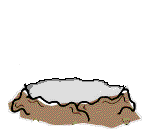 | 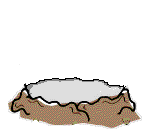 | 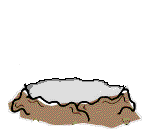 | 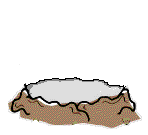 |
 | |||
山口は研究会の幹事でもあり、毎回 出席しているが、佐川が参加したのは久しぶりだ。佐川が感じたのは無力であることだ。
4年前、未来から戻ってきたときは、30年間の知識を活用して自分の暮らしも、会社の仕事も、ISO審査も、より良くしようと思っていた。
 | ||
 | ||
情報発信するにしても、マスコミでもなければ行政の長でもなく認証制度の幹部でもない。一企業の役付きでない社員に過ぎない。
これからの30年間で最大のイベントは、間違いなく東日本大震災だろう。犠牲者を減らす、被害を減らす、原発をどうすべきか、考えても良い方法は浮かばない。
それどころかサイズははるかに小さいISO認証においても、誤った解釈、規格にないことを要求する、何か問題があればすべて認証していた企業の責任にしてしまう認証制度そしてマスコミなどの態度、そんな問題を改善しようとは思っても方法は見えない。
![]() 本日の解説
本日の解説
私の書いていることを荒唐無稽とお考えのあなた !
人生いろいろ ISOいろいろ
イジメる人いろいろ イジメられる人いろいろ
困ることばかりだ。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の二十一第4号「管理票の交付を担当した者の氏名」 | ||||||||||||||
| 注2 |
1990年にマニフェスト票が法で定められた時から、法令で押印の指定はなかった。 現在、廃棄物管理業協会が販売しているマニフェスト票の交付担当者欄は、氏名のみ印刷されている。 いつから変わったのか知らないが、2021年に売られていたものは、交付担当者欄の左端に氏名、右端に印が印刷されているのは確認している。 下図は紙マニフェストの最上段の右側の部分
2020年〜2021年にかけて、政府の行政手続きにおける書類の押印不要化が行われ、ほとんどの手続きで押印が不要となった。マニフェスト票を販売している業者も、これに合せて㊞の印刷をなくしたのかもしれない。 | ||||||||||||||
| 注3 |
必殺仕事人は仕事人そのものの正義感から無償で自発的に仕事(殺人)をした回もありますが、ほとんどは元締めからの指示を受け報酬をもらっています。 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |