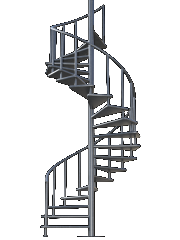注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
1997年10月下旬
佐川は山口から相談があると言われて、ロビー階の小会議室にいる。何故ここにいるかと言うと、理由はある。
二人はコーヒーのルームサービスを頼む。社内の人だけの打ち合わせでは、ロビーや会議室で飲み物やケーキを頼んではいけないというルールだが、その意味は部門費に付けるなと言うことだ。自腹なら文句はない。
各フロアにあるパントリーの給茶機は、半年ほど前にインスタント方式からミル挽き方式に替わった。
それで旨くはなったが、やはり金を払う方が美味い。容器は紙コップではなく磁器だし、ミルクもポーションミルクではなく本物だし、ミルクピッチャーも磁器だ。
| 飲み物の容器 | ミルクの容器 | お味 | |
| ロビーのコーヒー |  |  |  おいしい★ |
| パントリーのコーヒー |  使い捨ての紙コップ | 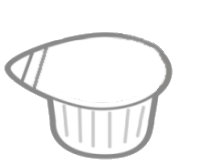 ポーションミルク 正体は水と油である |  ★イマイチ |
コーヒーが届くと、まずは香りを楽しみ一口飲んで話を始める。
![]() 「いいねえ〜、お金を払ってもここのコーヒーだな。アップルパイも良い」
「いいねえ〜、お金を払ってもここのコーヒーだな。アップルパイも良い」
![]() 「高松工場から認証機関を替えたいと相談がありました」
「高松工場から認証機関を替えたいと相談がありました」
![]() 「お好きなようにと言いたいが、今年審査を受けて認証したばかりだよね。ずいぶんと早いな。
「お好きなようにと言いたいが、今年審査を受けて認証したばかりだよね。ずいぶんと早いな。
なにかトラブルがあったの?」
注:多くの会社では認証機関の選定は工場の裁量ではない。将来の全社認証とか出向者の関わりがあるから、本社が仕切っているのが普通だ。
このお話では、吉宗機械が工場の自由にしていることにした。
![]() 「高松工場はISO規格が正式に発行されて、すぐ今年2月審査を受けました(第87話)。審査以降に問題があったわけではありません。
「高松工場はISO規格が正式に発行されて、すぐ今年2月審査を受けました(第87話)。審査以降に問題があったわけではありません。
初回審査のとき、ふたつ不適合を出されました。契約書の収入印紙に消印がひとつしかないというものと、印紙金額が不足しているという不適合でした」

法律でハンコを 2カ所押せとは書いてない。なお、上下左右、どの辺に押印しても良い。
![]() 「あ〜、思い出した。山口さんに相談されて、経理に行って印紙税について教えてもらえって言った記憶がある」
「あ〜、思い出した。山口さんに相談されて、経理に行って印紙税について教えてもらえって言った記憶がある」
![]() 「そう、それです。結果として両方とも合法で全く問題がないと説明して、不適合を取り消してもらいました。
「そう、それです。結果として両方とも合法で全く問題がないと説明して、不適合を取り消してもらいました。
私は社内全工場と関連会社の審査の所見報告書を集めており、一部の情報を隠してグループイントラネットにアップしています
高松工場はそれをみて、高松工場を審査したJ〇〇認証機関が、審査ミスで不適合でないのに不適合を出している割合が他の認証機関より高いことに気づきました。
それと審査の態度がタカピーで反論を許さない態度を取るという苦情が多く寄せられていました。
そんなわけで認証機関を替えようという結論になったそうです」
![]() 「論理としてはまっとうだな。こんなこと言っちゃまずいけど、高松工場から言ってきたということは、山口さんはそういうことをウオッチしていないの?」
「論理としてはまっとうだな。こんなこと言っちゃまずいけど、高松工場から言ってきたということは、山口さんはそういうことをウオッチしていないの?」
![]() 「あっ、もちろん私は所見報告書を入手するたびに、内容を見て各認証機関の評価をしています。
「あっ、もちろん私は所見報告書を入手するたびに、内容を見て各認証機関の評価をしています。
ただまだ審査は一回目ですからね、認証機関を見直すには早いと思っていました」
![]() 「失礼した。良くやっていると思いますよ。
「失礼した。良くやっていると思いますよ。
しかし1度のミスで鞍替えと言うのもな……」
![]() 「実はそのとき私が代理で交渉したのですが、まず言われたのが『言い訳しに来たのか』でした。それから不適合を出したのが間違いと分かっても、なかなか首を縦に振りませんでした。
「実はそのとき私が代理で交渉したのですが、まず言われたのが『言い訳しに来たのか』でした。それから不適合を出したのが間違いと分かっても、なかなか首を縦に振りませんでした。
最後に、不適合を出されたことの損賠賠償の話をしたら、完璧な拒絶でしたね。
そんなことで私もいい感じを持っていません。
更にですよ、高松工場はJ〇〇認証機関が他でどんな審査をしているのか、グループ企業以外の取引先とか近隣工場などの伝手で相当数の審査結果を入手して分析していました。
その結果、J〇〇認証機関が出した不適合のナンセンスコール割合は他の認証機関に比べて6割り多い結果だそうです。そこまでは私も統計を取っていませんでした。
それから高松工場に審査に来た![]() 鈴木審査員は、傲慢で他人の話を聞かないと評判が悪いです。
鈴木審査員は、傲慢で他人の話を聞かないと評判が悪いです。
とまあ、そんなことで、私は高松工場の鞍替えを支持します」
![]() 「じゃ、鞍替えしても良いと回答して粛々と進めたらいいじゃないか。今から急いでも認証機関を見つけるのが大変だろう。
「じゃ、鞍替えしても良いと回答して粛々と進めたらいいじゃないか。今から急いでも認証機関を見つけるのが大変だろう。
どの認証機関も、来年(1998)いっぱいは認証したいという注残が多いでしょう」
![]() 「実はわけありなんですよ。
「実はわけありなんですよ。
高松工場がJ〇〇認証機関を選んだのは、元高松工場長だった標準品事業部長の藤本さんなのですよ。J〇〇認証機関は我々とは関係ない業界系ですが、なんでも藤本さんが以前仕事でお付き合いがあった方が認証機関の社長だそうです」
![]() 「悪い意味で日本的だな。正直言って、私じゃ手に負えないよ。吉井部長の出馬だな」
「悪い意味で日本的だな。正直言って、私じゃ手に負えないよ。吉井部長の出馬だな」
![]() 「それがですね、来年春に環境部がCSR本部に格上げになるそうです。環境だけでなく社会貢献と働き甲斐のある職場担当などが付加されるそうです。
「それがですね、来年春に環境部がCSR本部に格上げになるそうです。環境だけでなく社会貢献と働き甲斐のある職場担当などが付加されるそうです。
吉井部長が本部長に昇進予定です。ということで昇進前にあまり波風立てたくないと」
![]() 「外国かぶれの吉井部長にしては日本的だな。要するに佐川が泥を被れということか。
「外国かぶれの吉井部長にしては日本的だな。要するに佐川が泥を被れということか。
いいよ、話すのは気にしないし、仕事では縁がないから査定が悪くなることもないでしょう」
その日の午後、佐川は人事部次長の下山に会う。
![]() 「俺が君に会いに行くのはしょっちゅうだが、君が来るのは珍しい。どんな用件かな?」
「俺が君に会いに行くのはしょっちゅうだが、君が来るのは珍しい。どんな用件かな?」
![]() 「悩み事相談です。
「悩み事相談です。
・・・・
ということで藤本事業部長にJ〇〇認証機関を切ることを了解してもらいたいのですが、それを補強する裏付けが欲しいのです」
![]() 「何をしてほしい?」
「何をしてほしい?」
![]() 「今、産業環境認証機関への出向者は8名です。J〇〇認証機関はもちろんゼロ。吉宗グループで審査を依頼しているのは、前者は48件、後者は8件です。
「今、産業環境認証機関への出向者は8名です。J〇〇認証機関はもちろんゼロ。吉宗グループで審査を依頼しているのは、前者は48件、後者は8件です。
依頼しているのは8件ですが、鞍替えしたいと言っているのは高松工場、関連会社は中堅製造業1社、規模としては小さい販売会社が2社です。年間の審査料金は合計で450万というところです。
4件しか依頼していない認証機関に出向者を出すのは厳しいし、そういう状況では出向者も辛いでしょう。
それで4社を鞍替えすることで産業環境に1名か2名追加で出向者を出せるということで藤本事業部長を説得しようと思うのです」
![]() 「お前も余計なことを考えたものだ。産業環境はそんなことせずとも、あと3名は出せることになっている。現実は出向候補がいないから8名に留まっているんだ。
「お前も余計なことを考えたものだ。産業環境はそんなことせずとも、あと3名は出せることになっている。現実は出向候補がいないから8名に留まっているんだ。
認証機関も取引先に過ぎない。下手な細工するのでなく、藤本さんにほんとの理由を伝えて、鞍替えを了解してもらえばいいじゃないか」
![]() 「分かりました。
「分かりました。
質問ですが、吉井部長は工場長級ですよね、藤本事業部長はそれよりワンランク上、まあ、立ち話できるレベルでしょう。
面識がなく
![]() 「本来は吉井部長が話さないといかんなあ……仕事の根回しなら君が向こうの同クラスの、まあ課長級か、そういった人と話をするのが普通だろうが、仕事でなく藤本さんの個人的な付き合いのこととなると、それも筋違いだな。
「本来は吉井部長が話さないといかんなあ……仕事の根回しなら君が向こうの同クラスの、まあ課長級か、そういった人と話をするのが普通だろうが、仕事でなく藤本さんの個人的な付き合いのこととなると、それも筋違いだな。
めんどくさいなあ〜
冷たいようだが、当たって砕けろ、勉強だと思って一度叱られ役をやってみろよ。何事も勉強だ」
![]() 「分かりました。メールでアポイント取ってみます。秘書っているのですかね?」
「分かりました。メールでアポイント取ってみます。秘書っているのですかね?」
![]() 「事業部長にはいないよ。たかだか二つ三つの工場を監督しているだけだ。普通にメールを送れば良いよ」
「事業部長にはいないよ。たかだか二つ三つの工場を監督しているだけだ。普通にメールを送れば良いよ」
![]() 「ご指導ありがとうございました。早速話をしてみます」
「ご指導ありがとうございました。早速話をしてみます」
注:事業部、事業本部など呼び名は多々あり、その上下関係なども会社によって全く異なる。
ここでは社長の下に事業本部があるとして、その下にいくつかの事業部があり、その下に複数の工場があると想定した。
事業部しかない会社、事業本部の下に工場がある会社などいろいろだ。
翌日の午後である。
標準品事業部の小部屋に藤本事業部長と佐川がいる。
![]() 「佐川君とは会うのは初めてだな」
「佐川君とは会うのは初めてだな」
![]() 「ハイ、初対面です。お願いがありまして参りました」
「ハイ、初対面です。お願いがありまして参りました」
![]() 「会ったことのない人からのお願いと言うとなんだろう?」
「会ったことのない人からのお願いと言うとなんだろう?」
![]() 「私は未来プロジェクト所属ですが、環境部も兼務しております。
「私は未来プロジェクト所属ですが、環境部も兼務しております。
昨年末にISO14001が制定されてから、日本中でISO14001認証のブームとなっています。
ISO認証とは民間資格のようなもので、審査して認証するのは民間企業です。どの認証機関から認証を受けても同じとされています。また認証機関を替えることも自由です。
ハッキリ言って認証とは電取とかJIS認定と違い、会社を評価するビジネスです。会社に対するサムライ商法と言えばお分りいただけるでしょう。
当社としては工場や関連会社が、どの認証機関から認証を受けても良いという指示をしております。
認証が始まってほぼ1年経ちまして、認証機関による善し悪しが目につくようになってきました。
認証は永久ものでなく有効期間が1年で毎年更新をします。それで認証開始初期に認証を受けた工場は、来年早々に1年後の審査の時期となります。評判の悪いところで審査を受けた事業所は、評判の良いところへの移転を希望しています。
それで言いにくいのですが、藤本事業部長が推薦されたJ〇〇認証機関で認証した中に、移転したいというところがありまして、それについて藤本事業部長のご了解を得たいということです」
![]() 「そりゃまた、ご丁寧なことだ。
「そりゃまた、ご丁寧なことだ。
具体的にはどこですか?」
![]() 「J〇〇認証機関から認証を受けているのは3工場あります。鞍替えしたいと言っているのは社内では高松工場だけですが、他に関連会社が3社ありまして、合わせて4件です」
「J〇〇認証機関から認証を受けているのは3工場あります。鞍替えしたいと言っているのは社内では高松工場だけですが、他に関連会社が3社ありまして、合わせて4件です」
![]() 「確かに私は高松工場にJ〇〇認証機関を検討してくれとは言ったが強制はしていない。それから関連会社に私は口をきいてはいないな。
「確かに私は高松工場にJ〇〇認証機関を検討してくれとは言ったが強制はしていない。それから関連会社に私は口をきいてはいないな。
ちょっと気になるけど、ダメな理由は何でしょうか?」
![]() 「高松工場ですが、今年初めの初回の審査で不適合が2件出されました。不適合とは認証できない大きな問題とご理解ください。
「高松工場ですが、今年初めの初回の審査で不適合が2件出されました。不適合とは認証できない大きな問題とご理解ください。
不具合のひとつは契約書に貼られた収入印紙の金額が不足で、脱税だということでした」
![]() 「収入印紙金額が不足となると
「収入印紙金額が不足となると
![]() 「いえいえ、そうではありませんでした。実際は印紙の金額は間違いなく、ISO審査員が契約書を請負と運送を間違えて不足と判断したのです。
「いえいえ、そうではありませんでした。実際は印紙の金額は間違いなく、ISO審査員が契約書を請負と運送を間違えて不足と判断したのです。
もうひとつは収入印紙の消印を2カ所に押してないということでした。
これも印紙税法でも税務署でも1か所で良いことになっています」
![]() 「つまり審査員のミスか」
「つまり審査員のミスか」
![]() 「そうです。高松工場は審査のクロージングミーティングで、その旨説明したのですが審査員が納得せず、不適合として審査を終わりました。
「そうです。高松工場は審査のクロージングミーティングで、その旨説明したのですが審査員が納得せず、不適合として審査を終わりました。
 審査終了後、高松工場から本社環境部に相談があり、環境部の担当者が認証機関を訪問して説明して取消してもらったという経緯です。
審査終了後、高松工場から本社環境部に相談があり、環境部の担当者が認証機関を訪問して説明して取消してもらったという経緯です。
関連会社についても、問題は違いますが不適合が出されました。それも審査員の誤判定ということで決着しています」
![]() 「そりゃ、アカンだろう。J〇〇認証機関は実力がないということか。
「そりゃ、アカンだろう。J〇〇認証機関は実力がないということか。
だけど認証機関だって、その後はそれを反映しているんじゃないの。敗者復活戦はあるのだろう?」
![]() 「まだ審査が始まって1年経過しておらず、どこも一度しか審査を受けておりません。しかし吉宗グループのISO審査結果はすべて本社環境部が把握しておりまして、どのような審査結果だったか、工場側の問題、審査側の問題を把握しています。そしてまとめたものを、発生場所を隠して、グループ内イントラネットに公開しています。情報を共有化して自ら点検してもらうことと、審査状況を理解してもらうためです。
「まだ審査が始まって1年経過しておらず、どこも一度しか審査を受けておりません。しかし吉宗グループのISO審査結果はすべて本社環境部が把握しておりまして、どのような審査結果だったか、工場側の問題、審査側の問題を把握しています。そしてまとめたものを、発生場所を隠して、グループ内イントラネットに公開しています。情報を共有化して自ら点検してもらうことと、審査状況を理解してもらうためです。
高松工場はそれをウオッチしていて、高松工場の審査以降も同様にミスを犯しているのを見て、来年早々の二度目の審査前に認証機関を替えたいと本社に相談に来たのです。
先ほど申しましたように、認証機関の選択は事業所の裁量としております。
工場や関連会社が決めれば良いわけですが、J〇〇認証機関は藤本事業部長のご推薦と伺っておりましたので、その説明とご了解を頂きたいと伺ったわけです」
![]() 「分かった、分かった。環境部の方に気を使わせて申し訳ない。それほどレベルが低いとは知らなかった。
「分かった、分かった。環境部の方に気を使わせて申し訳ない。それほどレベルが低いとは知らなかった。
そういうことを知らずに勧めていたとは恥ずかしい」
・
・
・
・
一仕事終えて佐川はホッとした。すぐに佐川は山口に電話する。
![]() 「佐川さん、お世話になります。早速、高松工場へ連絡します。正直言って今からでは鞍替えも難しいでしょうね」
「佐川さん、お世話になります。早速、高松工場へ連絡します。正直言って今からでは鞍替えも難しいでしょうね」
![]() 「それは高松工場が考える問題だ。
「それは高松工場が考える問題だ。
しかしこれは氷山の一角ですね。ウチの工場や関連会社だけでなく、研究会でも、認証機関のバラツキ、審査員のバラツキに困っています。どうしておかしな解釈とか規格にない要求事項を作ってしまうのですかね?」
![]() 「大先輩である佐川さんがご存じないことを、私が知るはずがありません。
ただ、情報の非対称性というのですか、現時点では認証制度側が審査を受ける側より圧倒的に優位にあります」
「大先輩である佐川さんがご存じないことを、私が知るはずがありません。
ただ、情報の非対称性というのですか、現時点では認証制度側が審査を受ける側より圧倒的に優位にあります」
![]() 「そうだろうか? 情報を持っているかもしれないが、それは間違いとか役に立たないものではないの?」
「そうだろうか? 情報を持っているかもしれないが、それは間違いとか役に立たないものではないの?」
![]() 「現実の審査を見ているとそうとも思えますね。でも、それを受け入れてしまう方は、全くと言ってよいほど情報がないから受け入れてしまうのも事実でしょう」
「現実の審査を見ているとそうとも思えますね。でも、それを受け入れてしまう方は、全くと言ってよいほど情報がないから受け入れてしまうのも事実でしょう」
![]() 「じゃあ、認証を受ける企業は、Guide62などを読めばよいということかな?」
「じゃあ、認証を受ける企業は、Guide62などを読めばよいということかな?」
注:Guide62は1996年制定だったはず。このお話の1997年には発行されていた。
ISO14001の審査規格であるGuide66は1999年発行だったと思う。
![]()
実を言って、私もguide62など知らなかった。審査でいろいろ問題があり、最終ミーティングで同意できないときどうするのか、異議申し立てをどうするのか、知る必要がありいろいろ調べた。
異議申し立ての窓口のない認証機関があったので、教えてやったこともある。
![]() 「現状は審査を受ける企業がISO14001そのものの理解がイマイチですから、審査のルールを定めた規格まで手が回るかどうか?」
「現状は審査を受ける企業がISO14001そのものの理解がイマイチですから、審査のルールを定めた規格まで手が回るかどうか?」
![]() 「でもそのために私たちはあのテキストを作ったはずだよね。
「でもそのために私たちはあのテキストを作ったはずだよね。
研究会で編纂したISO14001認証テキストは役に立たなかった、いや、不十分だったということなのかなあ〜
私はあれを読んでくれれば、マネジメントプログラムが2種類必要とか、スコアリング法でなければ人にあらずというような審査員を、退治できると思っていたのだけれど」
![]() 「もちろん役に立ちます。
「もちろん役に立ちます。
でも審査員のユニークな注文をネチネチと要求されると、受け入れたほうが楽かなと思うことは多いですね」
![]() 「何が問題だろうなあ?
「何が問題だろうなあ?
審査員のレベルが低いことに尽きるのか?」
![]() 「対応としては同意できなければ異議申し立てをすることでしょう。最近は工場でも本社にお願いしたいというところは減ってきました。自分たちの問題は自分たちでと言うことでしょう。
「対応としては同意できなければ異議申し立てをすることでしょう。最近は工場でも本社にお願いしたいというところは減ってきました。自分たちの問題は自分たちでと言うことでしょう。
でも異議申し立てだけでは効果がありません。やはり信賞必罰、ダメな認証機関は転注というか鞍替えすることでしょう」
![]() 「当然高松工場は次回の審査の通知が来たら、次回審査を依頼しないと言うだろう。するとJ〇〇認証機関から本社環境部にどうして依頼が来ないのかと電話が来るのではないかな」
「当然高松工場は次回の審査の通知が来たら、次回審査を依頼しないと言うだろう。するとJ〇〇認証機関から本社環境部にどうして依頼が来ないのかと電話が来るのではないかな」
![]() 「切ったからには、切った理由を話す必要を感じませんね。
「切ったからには、切った理由を話す必要を感じませんね。
彼らもなぜ客を逃がしたか想像つくでしょう。私が今年初めに訪問したときに、今後、対策が取られなければ
・
・
・
・
山口に説明した佐川は、人事の下山次長宛にお礼のメールを打つ。
下山さんのアドバイスに従い藤本事業部長に鞍替えをしたいと相談したら、状況を理解して快く賛同してもらえた。下山さんに感謝すると簡単にしたためた。
これで一件落着だ。
実は下山は佐川と話した後に、藤本事業部長に電話で認証機関鞍替えのネゴをしていたのだ。世の中は目に見える助け合いだけでなく、余計なお世話で成り立っているのだ。
・
・
・
・
その日の夕方、メールボックスをみると、結構メールが溜まっている。
山口からのメール
高松工場に鞍替えはOKと連絡した後に、切り替えを考えていた認証機関に話をしたら審査日程を確約してくれたのでそこに頼んだ、という報告だ。
その他、切り替え希望の関連会社からも、鞍替える認証機関の当てはあるから問題ないとのこと。
これで完全に1件落着だ。
・
・
・
・
 ハワード氏からメールが入っている。
ハワード氏からメールが入っている。
これは珍しい。とはいえ顧客をウチに回してよという営業メールかな?
メールを斜め読みするとそうではなかった。
要旨はISO14001認証が始まって1年近くなるが、とんでもない解釈を唱える認証機関や審査員が多い。このままではISO認証は、ブランドどころかゴミと化してしまう。なんとかしたいが上手いアイデアがない。
協力してほしいという、まさに佐川が思っていることだった。
もちろん佐川にアイデアがあるわけはないが、協力して何かできるならやるべきだ。
それなら産業環境認証機関の本間部長とかも混ぜた方が良いのではないだろうか?
ISO認証の押田編集長はどうだろうか?
そんなことを考える。
・
・
・
・
そんなことを考えてメールを片付けていくと、押田編集長からのメールもある。
吉宗機械に取材に行ったが掲載しなかったことを詫びる文句から始まり、佐川にコラムを書かないかというお誘いだ。
なんか今日はラブレターがたくさんだな。
もしISO認証に毎月コラムを書かせてもらえるなら、ふざけた規格解釈に反論することはできるかもしれない。
とはいえISO雑誌だって売れてなんぼだ。正論ばかり吐いても受けないと終わりだ。
さてどうするかなあ〜
![]() 本日、思うこと
本日、思うこと
私は日本のISO認証の黎明期から、企業の立場で携わってきたと言っても、過言ではないと思う。
審査では多種の問題があった。礼儀作法以前の暴言、
そういったものがISO認証の信頼性の低下、認証へのモチベーション低下、認証の評価を下げる、そういう流れにつながったと考えている。
そして最終的に認証件数の低下につながったのだ。
具体的に悪かったことを挙げてみる。
ひとつ、ISOMS規格の効用を実態以上に宣伝したことがある。
「ISOで会社を良くする」というのはその一例だ。ISO14001ではなぜか「会社が儲かる」という宣伝が多かった。
認証機関の社長自ら「会社を良くする審査をします」「経営に寄与する審査をします」と宣伝していた認証機関もある。
それってコンサルするという意味か? ならばISO17021違反になる。
そして騙ったことが実現しなければ契約不履行か?
ひとつ、まっとうな規格解釈をしない、あるいは規格を理解できなかった認証機関、審査員が多かったことだ。
認証機関の社長が「有益な環境側面」などを騙っていては手の打ちようがない。
既にその社長は引退してしまったが、過ぎたことは忘れたとは言わせないぞ。
ひとつ、企業不祥事をすべて企業の責任にして「企業がウソをついたから」と言い切った認証制度の人たちは、単細胞としか言いようがない。
証拠もなく騙った人たちを誣告罪で訴えたい。
他の人はどうあれ、私は自分の仕事を疑われた、否定されたと認識している。
うまくやれば長続きできた
今でも認証は続いているというかもしれない。
ベストセラーであったQMSでさえ、最盛期から半減した。認証制度の人はそれを体感しているだろう。審査が毎年減っているのだから。
 |
|
| 金字塔とはピラミッドのこと |
ではどうすれば好循環(virtuous cycle)したの
私はずっと考えてきた。
そもそもの認証制度の設計がまずかったのか。
認証の意義を明確に知らしめること、認証すると会社が良くなる、認証すると儲かる、そんな怪しいことを言わなければ良かった。
JIS訳も怪しくて問題が多々あった。
規格を正しく理解した人のみを審査員にする仕組み、認証の信頼性を把握し公表する仕組み(指標は要検討である)。
そういう仕組みの改善をすれば良かったのかなと思うけど、どうだろう?
ISOMS規格はくどいほど是正処置を語っている。
また、審査員は口癖のように「不具合を止めるにはシステムを直さなければならない」と語っている。
審査する側が是正処置できないわけはないだろう。
| それとも、できないのか |
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
所見報告書を公開したりコピー配布することは禁じられていない。ただ一部のみの配布や公開を禁じている。 だいぶ前だが、ほめられた部分だけウェブにアップして、ルール違反と指摘された自治体があったはず。 | |||||||||
| 注2 |
「スパイラルアップ」とか「負のスパイラル」という言い方は日本だけだそうだ。ISOに関して「スパイラルアップ」を語るのも、日本人だけだ。アメリカ、イギリスにはない。
らせん階段のらせんはヘリカルという。 ええカッコしようとして間違ったことを語って恥をかきたくはない。 スパイラルアップなんてISO規格にない言葉を騙っていないで、規格をしっかり読んで規格通りの審査をしてもらいたいものだ。 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |