注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
1997年12月下旬となった。上旬・中旬は最高気温10℃以上だったが、下旬となってからは最高気温は10℃を割り、最低気温は3℃程度で推移している。
そして行幸通りだけでなく株式市場にも木枯らしは吹く。1989年末にTOPIX(東証株価指数) は2,884という過去最高値を記録したが、それから8年もの間、下がるばかりで1997年末は1,100と、それ以降の最低値を記録した。
1997年は波乱な年であった。初夏に東南アジアの経済が本質的に弱体であるためにアジア通貨危機が起き、その影響で韓国が青色吐息、日本でもバブルの清算とも言える三洋証券破綻、山一証券倒産など大波乱があり、バブル崩壊から脱却できるかというとき、アジア通貨危機に足をすくわれた。
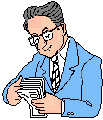 そんな中で、吉宗機械は
そんな中で、吉宗機械は
損益だけでない。既にアジア通貨危機で株価を下げていたところに、総会屋問題が発覚した多くの会社はブランドイメージを落としビジネスにもダメージを受けた。
これについても吉宗機械は、問題にされる前に自主的に問題を公表し対策をしている。そのため吉宗機械は不祥事を起こしたものの、しっかりした会社だという評価を得て、多少批判されたもののやり玉になることはなかった。
吉宗機械の経営者は未来が見えるのか、いやひらめきなのか?
同業他社に限らず、多くの会社や投資家が、吉宗機械に注目している。他社もマスコミも、吉宗機械の経営判断プロセスを知りたくてたまらない。
アジア通貨危機での成果は、しっかりと冬のボーナスに反省された。吉宗機械の一般社員は好調な理由を知らないが、組合と協定した算式に更に相当プラスされたボーナスを貰って大いに満足している。
未来プロジェクトと予言に対応した部署は、冬のボーナス以外に、特別賞与として所属部門統括の執行役からA4サイズの熨斗袋を手渡された。もっとも中身は明細書1枚だけだ。
とはいえ防いだ損失と投資益が千億近いのに、関係者がもらった特別賞与の総額は3,000万にもならないだろう。一般従業員へのボーナスアップ分を合せても10億そこそこだ。
お金に聡い財務部の連中は、会社は丸儲けだと冷ややかである。
佐川の特別賞与は100万プラスだった。入社以来29年、通常のボーナスの他にもらったのは初めてである。週末、佐川家はごちそうである。
食事の前に、佐川が二人の娘にポチ袋で小遣いを渡す。大学生の直美も高校生の里美も、なぜだ?という顔をしている。

![]() 「うーん、あと少し上積みしてくれたらグアムに行けたのに
「うーん、あと少し上積みしてくれたらグアムに行けたのに
![]() 「どうしたの、臨時のお小遣いなんて、クリスマスプレゼントなの?」
「どうしたの、臨時のお小遣いなんて、クリスマスプレゼントなの?」
![]() 「お父さんの働きが良いからボーナスが多かったのよ」
「お父さんの働きが良いからボーナスが多かったのよ」
![]() 「アジア通貨危機もあったし、お父さんの勤め先も総会屋問題で叩かれて、あまり良い年じゃなかったのにね。意外だわ」
「アジア通貨危機もあったし、お父さんの勤め先も総会屋問題で叩かれて、あまり良い年じゃなかったのにね。意外だわ」
佐川は、長年家庭をないがしろにしてきたが、少しは罪滅ぼしになったかと思う。
妻の洋子は、この成果は夫を支えた私のおかげと確信する。それは間違いない。
 年末年始休暇の数日前、佐川の社内用PHS電話が鳴った。
年末年始休暇の数日前、佐川の社内用PHS電話が鳴った。
佐川が電話を取ると、ハワードだった。
彼に最初に会ったのは1993年だから4年前(第36話)。その後、用があって認証機関に行ったとき偶然会ったこともある(第40話)。最後に会ったのはISO14001の制定前だ、彼が東京に出張したとき会って、その対応を話し合ったことがある。あれからもう2年になる。
用件は、審査で今、首都圏に来ている。明日の午前で審査が終わるので、午後3時には東京駅に着く。会えるなら会いたいとのことだ。
佐川は、もう年末で対外的な行事も社内会議もない。何か問題が起きなければ机上整理とかするだけだ。
3時過ぎに吉宗機械に来るということで約束した。
山口に電話すると、山口も予定がないから顔を出すという。
3時半、ロビー階の小会議室である。
挨拶もそこそこに、先日のメール(第98話)にあった本題に入る。
![]() 「先日、佐川さんにメールしたことだけど、他の認証機関のISO14001審査で、ユニーク解釈とか規格にない要求事項が飛び交っているようで、困っているよ。
「先日、佐川さんにメールしたことだけど、他の認証機関のISO14001審査で、ユニーク解釈とか規格にない要求事項が飛び交っているようで、困っているよ。
このままではISO14001の評価が落ちてしまうよ」
![]() 「JA〇〇という認証機関の団体がありましたね。そういう団体として是正を要求することはできないのですか?」
「JA〇〇という認証機関の団体がありましたね。そういう団体として是正を要求することはできないのですか?」
![]() 「団体そのものが、そういう人たちの集まりであるわけで・・・」
「団体そのものが、そういう人たちの集まりであるわけで・・・」
![]() 「思うのですが、ユニークな要求事項を言い出す人たちは、善意なのですね。彼らは会社を良くするとか、認証すると儲かるなんて言います。それはウソでもなく間違っているとも思っていないようです。
「思うのですが、ユニークな要求事項を言い出す人たちは、善意なのですね。彼らは会社を良くするとか、認証すると儲かるなんて言います。それはウソでもなく間違っているとも思っていないようです。
ISO認証の価値が大きいと言いたいのではないでしょうか」
![]() 「価値を大きく言いたいか……」
「価値を大きく言いたいか……」
![]() 「ハワードさんはISO雑誌など、お読みになられます?」
「ハワードさんはISO雑誌など、お読みになられます?」
![]() 「もちろん。当社が購読しているのはみっつありますね。
「もちろん。当社が購読しているのはみっつありますね。
『アイソムズ』、これは審査員対象も雑誌です。中身はまあ一回読めば十分で、毎月読むほど内容がありません。これは購読を止めたいです。
『アイソス』、これは審査員にも会社の方にも読んでもらおうという本のようです。ただ会社の人と言っても、一般の人じゃなくてISOマニアとか、審査員になりたい人向けのようですね。
これは一度当社に取材に来たので、おつきあいで購読しています。日本では義理といいましたっけ?
それから、半年ほど前に『ISO認証』が創刊されました。最初の数回はアイソス誌の二番煎じの感じでしたが、10月号から面白くなりましたね。
初めは曖昧だったターゲットを、一般の会社員に焦点を合わせたのが明白です。審査員対象の記事はなくなり、ISOのトラブル紹介とか赤裸々ですねえ〜、アハハハ
それから徒然草が面白い
![]() 「私は存じませんが、『ISO認証』の編集長と面識がありますから、聞いてみましょう?
「私は存じませんが、『ISO認証』の編集長と面識がありますから、聞いてみましょう?
ハワードさんと鷹派審査員対談なんて面白そうですね」
![]() 「同じ考えの審査員同士の対談じゃ面白くありません。ウチが審査を依頼している認証機関にも、おかしな解釈の方がいますね。そういった人たちをハワードさんが論破してほしいですよ」
「同じ考えの審査員同士の対談じゃ面白くありません。ウチが審査を依頼している認証機関にも、おかしな解釈の方がいますね。そういった人たちをハワードさんが論破してほしいですよ」
![]() 「本来なら公開の場で、おかしな審査員と討論したいです。でも彼らも商売ですから、アブナイことはしないでしょう。論破されたらそれ以降の仕事に差しさわりがありますからね。
「本来なら公開の場で、おかしな審査員と討論したいです。でも彼らも商売ですから、アブナイことはしないでしょう。論破されたらそれ以降の仕事に差しさわりがありますからね。
ISO14001は儲かると言っている人に、証拠を出せと言えば、回答はあってもISO14001と無関係な改善とかのはずです。
せめて同好の士ならと思いまして」
![]() 「私がおかしな解釈の認証機関に規格解釈を問い合わせしても返事が来ないのは、そういう理由ですか?」
「私がおかしな解釈の認証機関に規格解釈を問い合わせしても返事が来ないのは、そういう理由ですか?」
![]() 「そうだと思いますよ。他社と差別化したいからと、カッコいいこと、ユニークなことを語る。それを否定されると商売に困る。
「そうだと思いますよ。他社と差別化したいからと、カッコいいこと、ユニークなことを語る。それを否定されると商売に困る。
元はと言えば、ISO認証もISO審査も、どこに依頼しても本来同じものであるはずです。となると差別化はコストしかない。それよりも付加価値を付けてと言う発想なのでしょう」
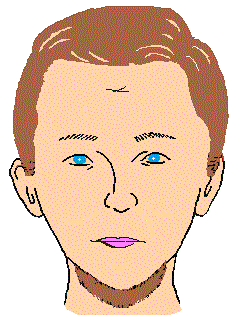 |  |  佐川 佐川 |
 山口 山口 |
注:某外資系認証機関のトップはGM(ゼネラルマネジャー)と称していた。支社長というところか?
![]() 「そもそも認証の価値、言い換えると認証の意義とはなんですかね?」
「そもそも認証の価値、言い換えると認証の意義とはなんですかね?」
![]() 「ISO9001の重鎮 加藤重信氏が『認証の価値は認証そのものだ』なんて語っていましたが、犬が自分の尻尾を追っかけているような堂々巡りです」
「ISO9001の重鎮 加藤重信氏が『認証の価値は認証そのものだ』なんて語っていましたが、犬が自分の尻尾を追っかけているような堂々巡りです」
![]() 「ではハワードさんの考える認証の価値とは何ですか?」
「ではハワードさんの考える認証の価値とは何ですか?」
![]() 「規格要求を満たしていると公に裏書することです」
「規格要求を満たしていると公に裏書することです」
![]() 「確かに審査登録証にそう書いてありますね。
「確かに審査登録証にそう書いてありますね。
それに疑問を持っているのですが、裏書することによる効果、言い換えると裏書者が保証するものは何でしょうか?
例えばULならUL認定品以外販売を禁止している地域で販売できるとか、事故が起きたら保険が降りるとかありますよね。ISO認証していると何が保証されますか?」
![]() 「裏書と言ってもその効果は、大中小いろいろあります。
「裏書と言ってもその効果は、大中小いろいろあります。
例えば生命保険は信頼できるといっても、約款とおりサッと払ってくれるわけではない。理由を付けて払わないとか減額とかあります。
審査登録証の価値は完ぺきではないけれど
![]() 「思うのですが、もしISO認証が認証を受けた会社の品質問題とか環境問題への損害補償などがあるなら、会社が儲かるなどと言う必要はないですよね。
「思うのですが、もしISO認証が認証を受けた会社の品質問題とか環境問題への損害補償などがあるなら、会社が儲かるなどと言う必要はないですよね。
会社が儲かるとか会社を良くすると語る認証機関の幹部は、自分たちの提供するものが確固たる価値があると、確信していないのではないでしょうか?」
![]() 「でも会社を良くするとか儲かるというなら、今度は自分が言い出したことに責任を負うよね?」
「でも会社を良くするとか儲かるというなら、今度は自分が言い出したことに責任を負うよね?」
![]() 「おっしゃる通り、だけど認証機関は自分が語ったことに責任を負う力もない。話を聞いた人だって、会社が儲かるとも良くなるとも思っていないでしょう。
「おっしゃる通り、だけど認証機関は自分が語ったことに責任を負う力もない。話を聞いた人だって、会社が儲かるとも良くなるとも思っていないでしょう。
認証制度は無力で悲しい存在と言うべきか」
![]() 「まずは自分の審査がIAFの基準を満たしているという確信、自信を持たないとならないよ。認証というサービスの価値がいかほどかは人によって評価が違うかもしれない。しかしまずは『認証の品質』が規格で定めた水準以上であることが必須だ。
「まずは自分の審査がIAFの基準を満たしているという確信、自信を持たないとならないよ。認証というサービスの価値がいかほどかは人によって評価が違うかもしれない。しかしまずは『認証の品質』が規格で定めた水準以上であることが必須だ。
審査員が規格要求を誤解していたり自分が考えた要求を加えたりしている現時点では、認証の価値を議論する前に、まずは審査の水準をあげ規格要求(下記注)を満たすようにしなければならない」
注:上記の規格要求とはISOMS規格ではなく、Guide66などの審査の規格要求のこと。
こんなことを書くと、自分は矜持を持って審査をしていたとか、真面目に仕事をしていたと反論が来るかもしれない。
だがお土産をねだるとか、規格要求以外を持ち出した審査員は、絶対にGuide62やGuide66に適合だったはずはない。
![]() 「だけど現実はユニークな要求事項で飾った中身のない審査、その認証がはびこる、まさに悪貨は良貨を駆逐しようとしています」
「だけど現実はユニークな要求事項で飾った中身のない審査、その認証がはびこる、まさに悪貨は良貨を駆逐しようとしています」
![]() 「残念だがそれが現実だ。だから私はそれを止めたい」
「残念だがそれが現実だ。だから私はそれを止めたい」
佐川の社内用PHSが鳴る。
電話に出ると受付からで、ISO認証誌の押田編集長が来ているという。
アポイントはなかったが年末の挨拶に顔を出したという。
ハワードにISO認証誌の編集長が挨拶に来たけど一緒に会うかと聞くと、会うというので受付にロビーにいるので上がってもらう。
ロビーのエレベーター前で山口が待っていると、押田編集長がエレベーターから出てくる。
![]() 「山口さん、お久しぶりです。わざわざ迎えに来てくれたのですか?」
「山口さん、お久しぶりです。わざわざ迎えに来てくれたのですか?」
![]() 「実は今そこでB〇〇社のゼネラルマネジャーのハワードさんが、年末の挨拶に来ているのですよ。
「実は今そこでB〇〇社のゼネラルマネジャーのハワードさんが、年末の挨拶に来ているのですよ。
お会いしたことがあるかと思います。
一緒にお会いしてよろしいですか?」
![]() 「いや、面識はありません。しかし良い機会です。ぜひともお会いしたい」
「いや、面識はありません。しかし良い機会です。ぜひともお会いしたい」
![]() 「それは良かった。案内します」
「それは良かった。案内します」
押田編集長とハワード氏は初対面だったようで名刺交換する。
![]() 「ハワードさんの御高名は聞いてますよ」
「ハワードさんの御高名は聞いてますよ」
![]() 「悪名の間違いじゃないですか、もっとも無名より悪名とも言いますか、アハハハ」
「悪名の間違いじゃないですか、もっとも無名より悪名とも言いますか、アハハハ」
![]() 「会社を良くするとか儲かるとか語っている認証機関への辛口の批判は聞いております」
「会社を良くするとか儲かるとか語っている認証機関への辛口の批判は聞いております」
![]() 「まあ、どこも商売のためとは分かっていますが、審査の基本から逸脱しちゃいけません。
「まあ、どこも商売のためとは分かっていますが、審査の基本から逸脱しちゃいけません。
お宅のISO徒然草を拝読しています。あれを書いている方も硬派というか正統派ですね」
![]() 「ひょんなことから良い方を見つけることができました。彼も日頃の審査でフラストレーションが溜まっているようです」
「ひょんなことから良い方を見つけることができました。彼も日頃の審査でフラストレーションが溜まっているようです」
![]() 「徒然草の筆者は実在しているのですか?」
「徒然草の筆者は実在しているのですか?」
![]() 「勿論です。先だって飲み会(第90話)がありましたね。あの時の若い記者の御父上です」
「勿論です。先だって飲み会(第90話)がありましたね。あの時の若い記者の御父上です」
![]() 「あっ、そうでしたか。例の研究会のメンバーは親子だろうと噂していました。あの飲み会で審査員批判を言うとすぐに反論したから、審査員が身内にいるはずだって」
「あっ、そうでしたか。例の研究会のメンバーは親子だろうと噂していました。あの飲み会で審査員批判を言うとすぐに反論したから、審査員が身内にいるはずだって」
![]() 「あのときは失礼しました。本人には注意しました。反省したようです。
「あのときは失礼しました。本人には注意しました。反省したようです。
ところで、ハワードさんも年末のご挨拶ですか?」
![]() 「そう言っちゃそうですが、ISO14001の審査で規格を理解していないとか、規格にない要求事項を追加している審査員がいて困ると、愚痴をこぼしていたのです」
「そう言っちゃそうですが、ISO14001の審査で規格を理解していないとか、規格にない要求事項を追加している審査員がいて困ると、愚痴をこぼしていたのです」
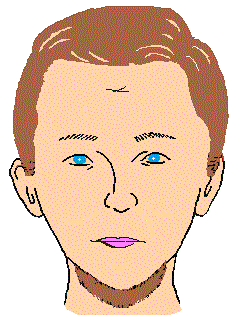 |  |  佐川 佐川 |
 |  山口 山口 |
![]() 「徒然草の主張そのままですね。徒然草も2ケ月ほどは原稿が決まっていますが、その先の回あたりで増子さんと対談などいかがですか?
「徒然草の主張そのままですね。徒然草も2ケ月ほどは原稿が決まっていますが、その先の回あたりで増子さんと対談などいかがですか?
距離が遠いですが、今はリアルでなくてもネット会議
![]() 「実は押田さんがお見えになる前、山口さんとそんな話をしていたのですが、同じ考えの人と意気投合しても面白くないでしょう。
「実は押田さんがお見えになる前、山口さんとそんな話をしていたのですが、同じ考えの人と意気投合しても面白くないでしょう。
押田さんがおっしゃったような、おかしな審査員と対談したいと話していたのです」
![]() 「それは無理ですね。論破された方は商売あがったりです。対談がそんなふうになると、相手から掲載しないように言われてしまいます」
「それは無理ですね。論破された方は商売あがったりです。対談がそんなふうになると、相手から掲載しないように言われてしまいます」
![]() 「押田さんは、ISO規格の間違いを広める人たちを、正す方法をご存じありませんか?」
「押田さんは、ISO規格の間違いを広める人たちを、正す方法をご存じありませんか?」
![]() 「悪貨は良貨を駆逐すると言いますが、何事も正しいことより自分に都合よい解釈が大衆に膾炙するのですよ。2000年も前にシーザーが『多くの人は、見たいと欲する現実しか見ていない』って言いました。
「悪貨は良貨を駆逐すると言いますが、何事も正しいことより自分に都合よい解釈が大衆に膾炙するのですよ。2000年も前にシーザーが『多くの人は、見たいと欲する現実しか見ていない』って言いました。
ISO認証すればどんなメリットがあるかが一番の関心ごとでしょう。第三者が会社の仕組みを合格と評価してくれたということより、儲かります、会社が良くなりますという方が客を呼べます」
![]() 「でもねえ〜、ISO14001で儲かるとか会社が良くなるとか言っていると、ISO認証ビジネスが先細りになりますよ」
「でもねえ〜、ISO14001で儲かるとか会社が良くなるとか言っていると、ISO認証ビジネスが先細りになりますよ」
![]() 「それは心配することですか? ISO14001が認証始まってまだ1年経っていませんが、今月末の認証件数は500件、伸びる一方ですよ。ISO9001と違い、非製造業、銀行や商社などが認証を受けようとしていますから、市場は数倍です。
「それは心配することですか? ISO14001が認証始まってまだ1年経っていませんが、今月末の認証件数は500件、伸びる一方ですよ。ISO9001と違い、非製造業、銀行や商社などが認証を受けようとしていますから、市場は数倍です。
吉澤先生なんてISO9001を追い越すなんて言ってますよ」
注:吉澤 正先生は集会や講演で、よくそんなことを語っていた。吉澤先生だけが読み違ったのでなく、多くの認証機関の人たちもそう考えていたようだ。
ISO9001の大成功があったからそう言ったと思う。だけど論理的に考えれば分かるはずだ。ISO9001と違い認証する必要も意味もないのだ。
![]()
そこで認証させようと「ISO14001は儲かる」と言ったのだろうが、儲かった事例を聞いたことがない。会社を良くすると言われても株価が上がったとか、特許が増えたともきかない。
![]()
そもそも規格要求事項を見ても事故が起きないとか違反が減るかとは思うが、株価が上がるとも売り上げが伸びるとも思えない。
![]()
ただ
![]() 「短期的にはそうでしょうけど、5年10年と大事に育てていかないと、あっという間に認証返上の嵐になりますよ」
「短期的にはそうでしょうけど、5年10年と大事に育てていかないと、あっという間に認証返上の嵐になりますよ」
![]() 「ISO9001はもう認証件数の加速度はほぼゼロになりましたからね」
「ISO9001はもう認証件数の加速度はほぼゼロになりましたからね」
![]() 「加速度がゼロとは?」
「加速度がゼロとは?」
![]() 「加速度がプラスなら下に凸のカーブですが、マイナスになると上に凸のカーブになります。プラスからマイナスに変わる点が変曲点。今変化がほぼゼロですからまもなくマイナスになる。加速度がマイナスになれば認証件数が減るということです」
「加速度がプラスなら下に凸のカーブですが、マイナスになると上に凸のカーブになります。プラスからマイナスに変わる点が変曲点。今変化がほぼゼロですからまもなくマイナスになる。加速度がマイナスになれば認証件数が減るということです」
 |
 |
短期的には急増していても、長期的な変化は
増減の増減、すなわち加速度を見なければな
らない。★★★★★★★★★★★★★★★★
この絵はいくつも絵を組み合わせているのだ
けど、一枚の絵にした方がサイズも小さくな
るかな?★★★★★★★★★★★★★★★★
![]() 「それは数学の話ですね。実際は違うかもしれない」
「それは数学の話ですね。実際は違うかもしれない」
![]() 「どんな道を辿ろうと、加速度がマイナスになれば時間が経てば認証件数が減るのは決まりです」
「どんな道を辿ろうと、加速度がマイナスになれば時間が経てば認証件数が減るのは決まりです」
![]() 「それを止める方法は?」
「それを止める方法は?」
![]() 「まずはまともな審査をすることでしょうね」
「まずはまともな審査をすることでしょうね」
![]() 「そうすれば止まるという保証はありますか?」
「そうすれば止まるという保証はありますか?」
![]() 「保証と言われてもありませんが、まともな審査をしなくてはそれ以前でしょう。
「保証と言われてもありませんが、まともな審査をしなくてはそれ以前でしょう。
だから『まずは』と言ったのです」
![]() 「ハワードさんは、ISO認証すると儲かるとか会社が良くなるというのを、止めろということですね」
「ハワードさんは、ISO認証すると儲かるとか会社が良くなるというのを、止めろということですね」
![]() 「そればかりじゃなくて、規格を理解すること、そして規格にないことを要求しないことでしょうね」
「そればかりじゃなくて、規格を理解すること、そして規格にないことを要求しないことでしょうね」
| 押田はしばし沈黙 やがて口を開く。 | 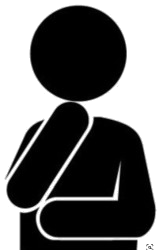 |
![]() 「どうすれば、まともな審査をするようになりますかね?」
「どうすれば、まともな審査をするようになりますかね?」
![]() 「すべての認証機関がまともな審査をしようと決心すること、すべての審査員が審査の基本を体得し実行することでしょうね」
「すべての認証機関がまともな審査をしようと決心すること、すべての審査員が審査の基本を体得し実行することでしょうね」
![]() 「当たり前のことですか」
「当たり前のことですか」
![]() 「当たり前のことを当たり前にする、凡事徹底ですね」
「当たり前のことを当たり前にする、凡事徹底ですね」
![]() 「粒粒辛苦、積土成山、コツコツ努力するしかないと」
「粒粒辛苦、積土成山、コツコツ努力するしかないと」
![]() 「『当たり前のことを当たり前にするのを止めろ』と語った人もいますよ」
「『当たり前のことを当たり前にするのを止めろ』と語った人もいますよ」
![]()
|
まずは『当たり前のことを当たり前にできること』が必要条件です。
まともな審査ができない人がそんなことを言ったら笑止です」
![]() 「押田さん、現状打破する方法がありませんか?」
「押田さん、現状打破する方法がありませんか?」
![]() 「私も現状の問題は認識しているつもりです。それにはしっかりした規格の理解です。
「私も現状の問題は認識しているつもりです。それにはしっかりした規格の理解です。
まずはまともな規格解説を掲載しようと思いました。徒然草はその手始めです。
あまり過激なことはできませんし、『会社を良くする派』を否定したくないのです」
![]() 「御社もビジネスですからね」
「御社もビジネスですからね」
![]() 「私たち業界の研究会でISO14001解説本を出しましたが、審査であれを否定する審査員はザクザクいますね。
「私たち業界の研究会でISO14001解説本を出しましたが、審査であれを否定する審査員はザクザクいますね。
徒然草はまっとうでも、その主張が世の中で通るかとなると疑問です。間違えている人の声は大きいですから」
![]() 「ISO認証誌のページを買って記事広告はできますか?
「ISO認証誌のページを買って記事広告はできますか?
記事広告と言っても公開質問状とかを載せて、挑戦するとかしたいですね」
![]() 「そりゃ商売ですからOKと言いたいところですが、敵を作るのは困りますね。私は認定機関とか認証機関と話ができる状況を維持しないと仕事になりませんから。
「そりゃ商売ですからOKと言いたいところですが、敵を作るのは困りますね。私は認定機関とか認証機関と話ができる状況を維持しないと仕事になりませんから。
記事広告でなく、広告の中で規格解説をされるなら問題ないですが」
![]() 「完全な広告では読んでもらえるのかどうか・・・
「完全な広告では読んでもらえるのかどうか・・・
それに徒然草は書いてお金がもらえるけど、それではお金を払って書くわけですな」
注:「広告でまっとうな規格解説」をしていたのは皆無ではなかった。新日本認証サービスの楢崎社長がアイソス誌に広告で規格解説とか規格を読むスタンスなどを書いていた。
効果があったかと言えば、まあ、多勢に無勢だったようだ。
![]()
なおこの新日本認証サービスはISO認証機関である。現在存在する新日本認証サービスは機械安全資格試験の会社で無関係のようだ。
![]() 「ウチは弱小雑誌ですから原稿用は安いですよ。徒然草は月5,000円です。
「ウチは弱小雑誌ですから原稿用は安いですよ。徒然草は月5,000円です。
対して広告ならA4で月15万、広告を出して1年に10社も増えれば元は取れるでしょう」
![]() 「効果があるのかないのか・・・」
「効果があるのかないのか・・・」
![]() 「ISOTC委員に、誤った規格解釈を諫めてもらうというのはできないでしょうか?」
「ISOTC委員に、誤った規格解釈を諫めてもらうというのはできないでしょうか?」
注:ISOTC委員は規格を作るだけでなく、その解釈について啓蒙する義務も、おかしな解釈については指導する義務もあるだろう。
だが知る限りおかしな解釈に物言いを付けた方を知らない。これは非常に疑問に思っている。唯一例外は、寺田さんが講演会で「有益な環境側面などない」と語っただけだ。
![]() 「彼らも敵を作りたくはないでしょうね」
「彼らも敵を作りたくはないでしょうね」
![]() 「みな無責任な八方美人か、困ったねえ〜」
「みな無責任な八方美人か、困ったねえ〜」
![]() 本日の疑問
本日の疑問
ISOTC委員とは規格を作る(改定もする)人たちだ。
そういう人たちは規格解釈を誤って使われ、審査され、不適合をバンバンと出されても気にならないのだろうか?
| 知らなかったですか |  |
なことはないでしょう。
有益な環境側面がないと不適合、有益と有害な環境側面を区別していない不適合と、本当は問題ないものがダメだしされていたことを知らないなら不勉強甚だしい。
著しい環境側面の決定は、スコアリング法以外をダメとしていた大手認証機関を知らなかったのですか?
それは浮世離れしていますよ。
2010年代半ば、某認定審査で認定審査員が認証審査員に「有益な環境側面を把握しているか質問しなかったのはまずい」と言ったと聞いた。
もしそうなら認定審査員も非常に怪しい。
寺田博さんが「有益な環境側面などない」と講演会で語ったとき、快哉を叫んだ企業のISO担当者がたくさんいたことも知らないのでしょうね。
お断り
私は有益な環境側面があると言っても犯罪だとは言わない。
だがISO審査において「有益な環境側面がないから不適合」とか、「環境側面に有益・有害の区別していないから不適合」と言われては、黙っていられない。
反論する方は有益な環境側面の根拠を提示願います。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
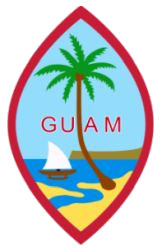 1990年代グアムは身近なアメリカであり、若者、家族連れの安くて安全な渡航先だった。そして価格も3泊4日で4万程のパックツアーがあった。
1990年代グアムは身近なアメリカであり、若者、家族連れの安くて安全な渡航先だった。そして価格も3泊4日で4万程のパックツアーがあった。だが2000年頃は80万人もいたグアムへの日本人観光客は、コロナ流行前の2019年には60万人と激減した。 コロナ流行が過ぎてもグアムの観光客は増えず、代わりに韓国、台湾、タイ、ベトナムなどへの渡航者が増えた。 その結果、グアムは便数も減り、パックツアーの価格も高くなるばかり。 | |
| 注2 |
企業向けのテレビ会議装置は1990年頃から結構普及していた。もちろん小さな出版社が持っているはずはない。 1995年にマイクロソフトがNetMeetingを出した。ISDNでないと実用にならないとか、画像が176×144ピクセルと小さいとか制限は大きかった。 一般人が実用したのは2003年に登場したSkype以降だろう。 スマホを使いLINEなどで簡単にテレビ電話できるようになったのは2010年以降だ。 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |