注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
| 西暦 | 世の中の出来事 | このお話の出来事 | 話数 | |||
| 1992 | 新幹線のぞみ登場 | 主人公佐川が若返る 課長解任され平となり、品質保証に異動 | 第1話 〜 第8話 | |||
| 1993 | EU統合 日本でインターネット始まる | ISO9001認証にチャレンジ 佐川の成果から本社応援、後に本社転勤 | 第9話 〜第43話 | |||
| 1994 | 関西国際空港開業 松本サリン事件 | ISO9001認証も一段落 | 第44話〜第47話 | |||
|
|
阪神淡路大震災 オウム真理教地下鉄テロ |
| 第48話〜第○話 | |||
| 1996 | 北海道豊浜トンネルで岩盤崩落 | ISO14001制定前からドラフト(草稿)で仮認証始まる 年末にISO14001制定される | ||||
| 1997 | ロシア船ナホトカ号沈没油流出 ペルー日本大使館事件 | ISO14001認証始まる | ||||
外資社員様から数日前にお便りをいただいた。
中に「未来は変えられるのか?」とあった。
それを読んでいろいろ考えた。
今書いているこのお話は、ISO認証に企業側で携わった者(私の投影である)が、老人になってから、なぜか30年前のISO黎明期に戻ってしまう。彼はISO認証制度が現れたときから、認証件数が半減するまでの過程を眺めていた。
なぜISO認証が退潮したのかと言えば、おかしな規格解釈で審査する認証側の問題、審査員を神と崇めていた企業側の問題、不祥事が起こると調べもせずに企業がウソをついたと騒ぐ消費者団体、そういったものがダメにしたとしか思えない。
主人公はその経験をいかして、おかしな解釈や審査を止めさせることができれば、ISO認証は企業に役に立つものとなったであろうこと、そして21世紀になっても低迷せずに興隆しただろうと考えるに至り、そのために活動しようとする。
ところで架空の話としても、その前提には「未来の知識を持って過去に戻れば、その情報によって困難は打破できる」という方程式が成り立つことが前提だ。
だがその前提は真だろうか?
今大流行のネット小説では、未来から来た人、あるいは文明の遅れた世界に行った人が、持っている知識を生かして、戦争に勝ち、発明・発見をする、農業に革命を起こす、良き政治家になる、芸術で大成する、ビジネスに活躍して大富豪になるというお話があふれている。
初期に書かれた小説には、具体的な技術とかノウハウを明確にしないまま、都合よく成功して、競争優位を確立してしまうものが多かった。だから突っ込みどころ満載で、人によってはバカバカしいと、すぐに放り投げてしまうシロモノが多かった。
それはつじつまが合わないというのではなく、知識だけでは物も作れず、ビジネスも成し遂げることはできないと認識しているからだろう。
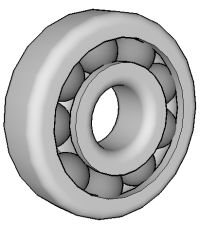
身の回りから多くの機械、家電品には小さなボールベアリングが使われている。
少しでも機械に関わったことがあれば、それを作るにはものすごい技術とノウハウが必要なことが分かるだろう。もしボールベアリングが消えたら我々の暮らしは何十年も前に戻る。いくら機械や便利な道具を思いついても、それがなければ実現できない。
だから最近の小説は突っ込まれないように進化してきて、法規制や社会常識という枷をかけた上で、それをクリアするようになった。
生物は環境に合わせて進化しないと生き残れないように、小説も進化してきた。
例えば2020年に生きていた人が1960年に戻ったらどうしたら良いか。
未来から過去に来た人が、成功するには知識だけでは不足だ。
ここで「2020年から1960年に時代をさかのぼること」だけは、超常現象として定理のように論証抜きで「ある」という前提とする。
そうでないと物語が始まらない。
まず文字通り今日、食うものの確保、という難問を乗り越えなければならない。
使えるお金を持っているだろうか? 電子マネーはない、クレジットカードはあっても田舎では使えない、まさに吉幾三の「おら東京さ行くだ」の状況だ。
2020年発行の野口英世のお札を1960年で使ったら子供のおもちゃと笑われる。偽札犯にもならないだろう


|
しかし発行年の刻印が「平成」や「令和」であれば、即座に偽造コインとされるだろう
当面のお金を確保したら、次の問題である。
働くにも住む家を借りるにも、住民票、免許証、マイナンバーカードのような身分証明をどうするかという問題になる。
医者にかかるにも、就職するにも、住所不明の人間が生きていくのは現代では無理だ。
小説では戦後のどさくさにまぎれる、他人の戸籍を買う、記憶喪失を装う、権力者を頼って戸籍を作ってもらうとかが定番だ。
まあ、それもクリアできたとしよう。
やっと新世界で人間として認められたわけで、いよいよその世界で生きていくことになる。
だが、難関はまだ続く。
未来の知識を生かすには、元手も必要だ。発明するにも場所も材料も手足も必要だし、特許を取るにもお金がかかる。
第53話で1995年に安くなったドルを買い、3年後の1998年に安くなった円に替えようとする話を書いた。
でも100万円が3年後に137万になって、37%の儲けだ。大儲けとは言えない。それに3年も待てるのか?
そもそも100万円の元手を確保するのも、未来から来たばかりで可能かどうか。そして37万円の利益を得てもあまりうれしくない。せっかく未来から来て大きなことをしようとするなら、せめて1億くらい欲しい。何をするにしても資金がないとどうにもならない。
未来からあるいは異世界から来た人が手っ取り早く、その時代の現地のお金を得るには、いくつかのパターンがある。
もちろん身に着けている未来のものを売るというのは最も基本だ
もちろん未来と行き帰りできるわけではないから、身に着けているものを売れば終わりだ。
賭け事も難しい。
まず宝くじは当選番号を覚えていても、望む番号を買えないからだめだ。ロトなら番号は自分が決められるが、その日の当選番号を覚えているはずはない。
いや、ロトが始まったのは2000年からだった、
 競馬は元手を増やす方法として多くの小説で使われる
競馬は元手を増やす方法として多くの小説で使われる
それと競馬で一着を知っているからと、万馬券を当てても効果がないかもしれない。当選者が少ないから配当が高いのであって、当たり馬券に大金を賭ければ手に入る金額は同じで配当率は下がるだけ
それと競馬は当選馬を知っているレースを逃せないという制約がある。発明・発見なら時期を問わないだろうが、競馬はそのレースに賭けなければならない。
同じく占いなら、いつ大地震が起きるかを知っていても、10年後では役に立たない。
また権力・権威も必要だ。
ネット小説では王とか戦国大名などに取り入るのがパターンである。雑兵ならともかく、無名ならいくら剣術が強くても軍師ができても雇ってくれない。〇流免許皆伝とか武将の推薦が欲しい。
実例を挙げよう。
20世紀末から2010年頃まで、「有益な環境側面」という邪教というか妄想が猖獗を究めていた。私は当時、審査の場で有益な環境側面と有害な環境側面を識別するように要求され、そんなものないと審査員を説得しようとしたが、アホ審査員は理解できなかった。
| 有益な環境側面と有害な環境側面を 区別しないと、不適合なんだってよ | |||
|
だが寺田博さんが某所の講演会で「有益な環境側面はない」と語って以降、有益な環境側面信者はナメクジに塩をかけたように静かになった。
内容や理屈ではない。かように権威の力は大きい。いや、寺田さんの人徳かな。
かように「未来を変える」ことは極めて困難なことなのだ。
このバカバカしい小説でも、そこをうまくクリアしないと様にならない、いや話が荒唐無稽に空中分解してしまう。
言い換えれば、知識、元手、機会、権威をまとめれば小説もまとまるだろうし、現実のISOも良くなったに違いない。
この小説が形になるよう、頑張らねばならない。

業界団体の研究会発足から数日後、吉井部長が佐川を自席に呼んだ。
部長席の脇にはいつもパイプ椅子が置いてある。少人数の秘密でない話は部長席でするのだ。
![]() 「研究会が始まったが、何か進展はあったか?」
「研究会が始まったが、何か進展はあったか?」
![]() 「いえ、まだなにも……先日顔合わせをしただけです。一応第2回目までに、それぞれがDIS(規格案)を読んで、皆で読み合わせしようという話になりました」
「いえ、まだなにも……先日顔合わせをしただけです。一応第2回目までに、それぞれがDIS(規格案)を読んで、皆で読み合わせしようという話になりました」
![]() 「成果は出そうか?」
「成果は出そうか?」
![]() 「他社から来た人たちは一様に規格の曖昧さ……まあ誰でもどこでも使えるようにとなると、そうなってしまうものですが……を指摘していました。
「他社から来た人たちは一様に規格の曖昧さ……まあ誰でもどこでも使えるようにとなると、そうなってしまうものですが……を指摘していました。
そしてそれによる認証機関や審査員による、解釈の違いやバラツキが問題になると認識していますね。
おっと私がこれから起きることを話してはいません」
![]() 「皆の考えていることは、君の体験と同じということか?」
「皆の考えていることは、君の体験と同じということか?」
![]() 「その通りです。実際に私と同じくISO9001の審査を体験した人もいますし」
「その通りです。実際に私と同じくISO9001の審査を体験した人もいますし」
![]() 「ということは審査が始まればトラブル多発することか?」
「ということは審査が始まればトラブル多発することか?」
![]() 「確かに参加メンバーにとっては大問題となりますが、審査の場でトラブルにはならないでしょう」
「確かに参加メンバーにとっては大問題となりますが、審査の場でトラブルにはならないでしょう」
![]() 「ええと、それはどういう意味かな?」
「ええと、それはどういう意味かな?」
![]() 「前世では研究会が考えたISO14001認証間違いなしと考えた手法は、審査が始まると同時に審査員に完璧に否定されてしまいました。
「前世では研究会が考えたISO14001認証間違いなしと考えた手法は、審査が始まると同時に審査員に完璧に否定されてしまいました。
審査で否定されてしまったのですから、もめるわけありません」
![]() 「それは認証機関の考えに合わせるしかなかったということか?
「それは認証機関の考えに合わせるしかなかったということか?
だが君の話では認証機関によって見解は異なるというから、別の認証機関を選んだ会社は上手くいったのだろう?」
![]() 「業界傘下の会社は、業界設立以外の認証機関を使えません。いや他の認証機関への依頼が禁じられているわけではありません。しかし出向者を出した企業はそうはいきません。業界設立の認証機関の考えに合わせるしかありません。
「業界傘下の会社は、業界設立以外の認証機関を使えません。いや他の認証機関への依頼が禁じられているわけではありません。しかし出向者を出した企業はそうはいきません。業界設立の認証機関の考えに合わせるしかありません。
転注できないのは社内の問題かもしれませんが」
![]() 「そういうことね……
「そういうことね……
それで前世ではどうしたの?」
![]() 「私はいろいろな資料を作り、また他の認証機関の考えをまとめて、業界で作った認証機関に説明を行ったのですが、すべて否定されてしまいました」
「私はいろいろな資料を作り、また他の認証機関の考えをまとめて、業界で作った認証機関に説明を行ったのですが、すべて否定されてしまいました」
![]() 「そこが分からないのだが、否定するとはどういうことかね?」
「そこが分からないのだが、否定するとはどういうことかね?」
![]() 「単純にその解釈は間違っているからダメですと、言われたわけです。それ以降は相手にされませんでした」
「単純にその解釈は間違っているからダメですと、言われたわけです。それ以降は相手にされませんでした」
![]() 「だが他の認証機関は別の解釈なのだろう。だったら己の解釈が絶対正しいとは言えないじゃないか?」
「だが他の認証機関は別の解釈なのだろう。だったら己の解釈が絶対正しいとは言えないじゃないか?」
![]() 「泣く子と地頭には勝てないとか、頭の良い人を説得するのは難しいが、頭の悪い人を説得するのは不可能とも言います。
「泣く子と地頭には勝てないとか、頭の良い人を説得するのは難しいが、頭の悪い人を説得するのは不可能とも言います。
ともかく道理の通じない相手は説得できません。
他の認証機関の見解を示しても、我々は違うと言われるともう話は終わりです。我々が正しいと考え他の認証機関がOKする方法にするには、認証機関を替えるしか道はありません。
それから他の認証機関は、あそこは考えがおかしいと陰では言いますが、面と向かって他社を批判しません」

吉井部長は腕組みをして沈黙する。
佐川は吉井部長の気持ちは分かるが、解決策がないのも分かっている。
![]()
佐川は断って席を立ち、パントリーからホットコーヒーを二つ持ってくる。
![]() 「先ほどの続きですが……他人に迷惑をかけるのを気にしなければ、民事訴訟でしょうね。それしかありません」
「先ほどの続きですが……他人に迷惑をかけるのを気にしなければ、民事訴訟でしょうね。それしかありません」
![]() 「争点は何だ?」
「争点は何だ?」
![]() 「審査依頼をするには審査依頼の契約をします。契約内容は、審査規格ISO○○による審査を委託しますというものです。
「審査依頼をするには審査依頼の契約をします。契約内容は、審査規格ISO○○による審査を委託しますというものです。
審査でOK/NGを判断する審査基準とは、規格要求事項だけでなく、法規制、そして当社が規定や要領書で決めたルールが該当します。
それ以外の契約にないことを持ち出すのは契約違反です。
これから制定されるのですが、ISO14001の審査について決めたガイド66
但しその場合は追加する審査基準を書面で公表しなければならないとあります。そりゃそうですね、予め条件を示しておかなければ、怖くて契約できません。
私の前世では、独自の審査基準を追加すると表明した認証機関はありませんでした
![]() 「実際はどの会社も、契約違反だと言わなかったということか?」
「実際はどの会社も、契約違反だと言わなかったということか?」
![]() 「他社は知りません。私はそういう問題が起きたとき、審査員とそういう議論はしました。まあ、カエルの顔に小便です」
「他社は知りません。私はそういう問題が起きたとき、審査員とそういう議論はしました。まあ、カエルの顔に小便です」
![]() 「上には言ったのか?」
「上には言ったのか?」
![]() 「もちろんです。なにしろ趣味とか気分の問題ではなく、すべてお金につながります。就業規則に『過失により会社に損害を与えたとき懲戒に処す』とあるでしょう。
「もちろんです。なにしろ趣味とか気分の問題ではなく、すべてお金につながります。就業規則に『過失により会社に損害を与えたとき懲戒に処す』とあるでしょう。
 |  |
ここから問題です。上長命令が文書で残れば、部下は命令に従わなくても就業規則通りですし、刑法上も無罪です。しかし当時の上長は例の尾関さんでしたから、審査員が言われるとおりにと言いながら、責任を取るはずがありません。
法規制に関わることで、審査員の間違いもありました。尾関さんはそれも審査員の言う通りにしろと言われました。しかたがないから審査員の言うように改造して、写真を撮って是正報告に添付しました。
当たり前ですが消防署から指摘されないよう、すぐ元に戻しました。
余計な工事をして、写真を撮ってまた元に戻すとは、環境に悪そうですね」
![]() 「元に戻さんとダメなのか?」
「元に戻さんとダメなのか?」
![]() 「そのままにしておいて行政の立ち入りで見つかれば、法違反の責任を問われて大問題になります。そのとき尾関さんは自分が指示したと言うはずがありません」
「そのままにしておいて行政の立ち入りで見つかれば、法違反の責任を問われて大問題になります。そのとき尾関さんは自分が指示したと言うはずがありません」
![]() 「尾関君がいなくなって心配事は一つ減っただろう」
「尾関君がいなくなって心配事は一つ減っただろう」
![]() 「正直言いまして、今は吉井さん次第ですね」
「正直言いまして、今は吉井さん次第ですね」
![]() 「しかしお前も苦労したせいで性格がねじ曲がったのだなあ〜」
「しかしお前も苦労したせいで性格がねじ曲がったのだなあ〜」
翌週である。
また佐川は吉井部長に呼ばれた。
吉井部長が佐川を呼ぶのは用があるからでなく、何か迷っていると佐川を相談相手にしているようだ。相談相手にするなら課長を呼べばいいのにと佐川は思う。
![]() 「環境部ができてふた月になるが、他の部門との取り合いが難しいなあ〜
「環境部ができてふた月になるが、他の部門との取り合いが難しいなあ〜
お前は何か考えることはないか?」
![]() 「理由は単純で環境部の仕事が、関連したひとつのカテゴリーではないからでしょう」
「理由は単純で環境部の仕事が、関連したひとつのカテゴリーではないからでしょう」
![]() 「ひとつのカテゴリーではないとは?」
「ひとつのカテゴリーではないとは?」

![]() 「現在の環境部の職掌は何かとなりますと、多種多様なもののごった煮でとりとめがありません。
「現在の環境部の職掌は何かとなりますと、多種多様なもののごった煮でとりとめがありません。
公害防止は元々、生産技術の一部門でした。例えば汚染防止なら、汚染物質を外部に出さないことですが、真の対策は外部流出を止めるのでなく、発生しない製造を考えることです。
そのためには生産方法を変えることになり、生産技術の範疇でしょう。
廃棄物も、適切で合法な処理が目的でなく、発生させないことですから、設計や製造プロセスの見直しとなり、これも環境部が担当するのも筋違いです。
いかに廃棄物を出さないで生産するか、更に自社製品のリサイクルを考える時代です。環境部にできますか?
工場省エネはオイルショックをきっかけに、1979年に制定された省エネ法で義務でした。そのため過去より乾いたぞうきんを絞ってきました。ですから放っておいても省エネは進んでいきます。
そして現在は省エネの対象は広がり、重点は輸送や大規模ビルなどに移りつつあります
そして考えるまでもなく、省エネと廃棄物と化学物質は相互に無関係です。それを一緒にして管理できるわけありません」
![]() 「そういえば私がここに異動してきたとき、君と話してそんなこと言われたな(第45話)。
「そういえば私がここに異動してきたとき、君と話してそんなこと言われたな(第45話)。
君の意見は、環境部とは一時的なものだと記憶している」
![]() 「覚えていてくれましたか。そうです、環境部とは一時的な組織です。
「覚えていてくれましたか。そうです、環境部とは一時的な組織です。
従来、環境に関する仕事は設計、営業、物流、製造、工場管理などが、それぞれ関わることを処理していました。
ますます環境に対する会社の姿勢や活動が要求され、外部からウォッチされるため、それに対応する仕組を作るというのが環境部設立の流れだと思います」
![]() 「そうだ、そうだ、そうだった」
「そうだ、そうだ、そうだった」
![]() 「経理とか購買という機能は、江戸時代の商店でも具備している機能であり部署だったと思います。しかし環境というのは経理とか購買とかでなく、すべての部門が関わることなのです。
「経理とか購買という機能は、江戸時代の商店でも具備している機能であり部署だったと思います。しかし環境というのは経理とか購買とかでなく、すべての部門が関わることなのです。
最近セクハラ、セクシャルハラスメントが正しいそうですが……それを担当するのはどの部門でしょうか。人事とか最近ではコンプライアンス部門というのがある会社もあるそうですが、そういう部門が担当しているそうです。
しかし考えてみれば職場でセクハラをなくせというのは、人事の仕事でもコンプライアンス部門の仕事でもなさそうです」
![]() 「ほう、じゃ、どこの担当なんだね?」
「ほう、じゃ、どこの担当なんだね?」
![]() 「すべての部門ですよ。すべての部門の管理者が、法規制はもちろん社会倫理に沿って、部門を動かしていかねばなりません」
「すべての部門ですよ。すべての部門の管理者が、法規制はもちろん社会倫理に沿って、部門を動かしていかねばなりません」
![]() 「なるほど」
「なるほど」
![]() 「環境も同じなのですよ。環境先進企業に環境部門はないと言われます。環境に関わることが仕事の中に溶け込む、内部化されないと真の環境配慮じゃないのです」
「環境も同じなのですよ。環境先進企業に環境部門はないと言われます。環境に関わることが仕事の中に溶け込む、内部化されないと真の環境配慮じゃないのです」
![]() 「なるほど」
「なるほど」
![]() 「とはいえ、今は過渡期です。環境対応の仕組みの整備をして、働く人に意識付けする時期なのです。現状では、取り合いで軋轢が起きることは当然です。そこはそういうものと認識するしかありません。
「とはいえ、今は過渡期です。環境対応の仕組みの整備をして、働く人に意識付けする時期なのです。現状では、取り合いで軋轢が起きることは当然です。そこはそういうものと認識するしかありません。
過渡期において環境に関わることを調整し推進するのが環境部なのです」
![]() 「なるほど、以前君が話してくれた時も過渡期とは言ったが、そういうことまでは説明してくれなかったように思う」
「なるほど、以前君が話してくれた時も過渡期とは言ったが、そういうことまでは説明してくれなかったように思う」
![]() 「私も日々、吉井部長の判じ物のような指示を受けて難儀しております」
「私も日々、吉井部長の判じ物のような指示を受けて難儀しております」
![]() 「お前は一言多いんだよなあ〜」
「お前は一言多いんだよなあ〜」
![]() 本日の振り返り
本日の振り返り
誰でも「生まれ変わって」と思ったことはあるかもしれません。
でも生まれ変わっても、親もいれば妻も子供もいる。以前と違う決断、選択を自由にできるわけではありません。
私の場合、生まれ変わったら、もう少し勉強しようとか、もっと子供たちと遊ぼうとか思いますが、別の人と結婚すればとか、親との葛藤をなくすなんてできるとは思いません。物事にはすべて原因があって結果があります。過去がそうであったのには十分な理由があるわけです。
誰だって、今までの人生の岐路においては一生懸命考え、選択したと思います。ならば、生まれ変わっても、条件や環境が変わらなければ違う選択はなさそうです。
一度歩んだ人生がベースでほんの少し変わる程度ではないのかなと思います。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
刑法148条で通貨偽造・行使の罪が定めてある。 全く同一でなくても誤認されるものは罪に問われる。 | |
| 注2 |
フレドリック・ブラウンの「未来世界から来た男」を読んだ方ならご存じのネタ。 | |
| 注3 |
たくさん例があるがいくつか例を挙げる。 本や写真を売るもの。「老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます」 シャンプーや石鹸を売る「愛されることを知らなかった食いしん坊姫」 | |
| 注4 |
たくさんあるが競馬の例を挙げる。 「昭和38年 〜令和最新型のアラフォーが混迷の昭和にタイムスリップしたら〜」 「俗物夫婦回帰転生」 | |
| 注5 |
競馬のオッズはパリミュチュエル方式(総投票方式)といい、当たり馬券で配当金を割る。だから当たり馬券に大量の資金が投じられるとオッズが下がる。 例えば、100倍(万馬券)のオッズだった馬に大金を賭けた場合、その馬券の購入金額が全体の売上の中で大きな割合を占めるようになり、オッズが下がり万馬券でなくなることもある。 ただレースの売上規模が大きいG1などでは、個人が数百万〜数千万円を賭けても影響が小さく万馬券のままかもしれない。他方、地方競馬や掛け金が少ないレースでは、大きな資金が入るとオッズが大きく変動する。 ロトも同じで当選者が多いか一人が同じ番号で何口も買えば、得られる配当金総額は変わらないが一口あたりの配当金は下がる。 | |
| 注6 |
ISO審査を決めた規格はISO14010やISO14011などがあった。 その後、ガイド66が作られ、21世紀にISO17021に集約された。 ・ISO14010 ・ISO14011 | |
| 注7 |
厳密に言えば、ロゴマークの使用方法、審査登録証の配布方法などが該当するだろう。 | |
| 注8 |
輸送の省エネルギーが規制されたのは2006年の省エネ法改正が始まりである。これにより、トラック・バス・タクシー・鉄道・航空・船舶などの運輸業者が、省エネ対策を求められた。 具体的には、一定規模以上の運送事業者は、毎年「エネルギー使用量」の報告義務、燃費改善や低燃費車両(ハイブリッド・EV・LNGトラックなど)の導入、省エネ目標の達成が求めらた。 また大量に貨物輸送を委託する荷主(メーカー、卸売/小売業者)は貨物の輸送量を毎年集計し報告する義務がある。 |
外資社員様からお便りを頂きました(24.02.10)
おばQさま 個人が大きく未来を変える事は運しだいですが、個人の人生の分岐点は選べますよね。 >上長命令が文書で残れば、部下は命令に従わなくても就業規則通りですし、刑法上も無罪です これは私も経験しました、ウブな平社員だった時に部長に口頭で承認を貰ったのに、事業部の偉い人が怒って部長に聞いたら「僕は聞いていないよ」 当時は部長が卑劣な嘘をつくなんてと悲憤慷慨。 でも今ならば、そういう人だよねと割り切れるし、書面で記録を残す事をしたはず。 個人が出来る未来の変革って、この程度ですかね。 この問題は先の大戦でも起きて「私は貝になりたい」のB級戦犯の設定にも共通。 無辜の市民を爆撃した米軍飛行士を、部隊長から「戦争犯罪者だから殺せ」と口頭命令で実行。 敗戦後に「私は命令された」と言っても口頭命令だから、元隊長が否認すれば犯罪になる。 参謀ツジーンなんて、あちこちで口頭命令やら、私製命令出して捕虜殺害。 実行者はB級戦犯、もっと可哀そうなのは名義上の命令者の隊長。 私製命令だから本当に知らないけれど、記録上は隊長が出しているから「シランプリして部下を見殺し」と言われるか、「部下の罪を負って死罪」 そんな事があったのに、戦後の日本の会社で統制が甘い所は、私製命令や口頭命令が横行。 こういうものを問題に出来ない、そんな偉い人を生むのは「マネジメント」の問題、もちろんISOで監査出来ない。 それによる気の毒な人は、過去に遡って助けたいと思います。 または、今からでも良いから名誉だけでも回復するべきですね。 |
外資社員様 毎度ありがとうございます。 権限とか命令とはどうあるべきか定めても、運用によってグダグダになりがちですね。それをISO流に四角四面に運営するなら良いのでしょうが、多くの場合融通を利かせてしまいます。 ISO認証のお手伝いなんて何十回もしましたが、従来からしていたイレギュラーな運用(というかデタラメ)を、なんとか継続して不適合にならないようにしたい会社が多いです。 法治主義というより人治主義になってはメチャクチャです。と考えていると日本国憲法を思い出します。憲法改正が不可能に近いせいか、解釈改憲という手を使うのはずるいですよ。文字解釈で白黒つけなくちゃ憲法が泣きます。 最高裁判事の多くが合憲としているようですが、同性婚が現憲法でOKってのはないでしょう。「両性の合意に基づく」のを直さないと絶対におかしい。同性婚に反対じゃありませんが、現行憲法で合憲とはまったくおかしいです。なんで憲法改正して対応しないのか?不思議でなりません。 本題に戻れば、日本人は白黒つけるのが苦手なのかなあ〜。それで済むときは良いけれど、問題ですよ。 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |
