注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
月曜日、増子が始業30分前に会社に着くと、既に押田さんは仕事をしていた。
 |
|
| デスクトップが、CRTから液晶に変わったのは2000年以降です。 それまではCRTの暖かさが冬は快適でした。夏は・・・ |
![]() 「押田さん、少しお話して良いですか?」
「押田さん、少しお話して良いですか?」
![]() 「ああ、いいとも、なんだろう」
「ああ、いいとも、なんだろう」
![]() 「先週の失礼を謝ります。
「先週の失礼を謝ります。
実は私の父はISO審査員をしています。それであそこで多くの人が審査員批判をされたので、気を悪くしました」
![]() 「なるほど、そういうことか」
「なるほど、そういうことか」
![]() 「それだけではありません。金曜日の夜、出張から父が帰宅してから一緒に飲んで、そんな話をしました。すると父が言うには、あそこで聞いたことの7割は目にしていると言うのです。
「それだけではありません。金曜日の夜、出張から父が帰宅してから一緒に飲んで、そんな話をしました。すると父が言うには、あそこで聞いたことの7割は目にしていると言うのです。
幸いというか、父はそういう審査員や審査を良く思ってはいないと言っていました。それで少し救われました」
![]() 「どの認証機関かは聞かないけど、契約審査員ですか?」
「どの認証機関かは聞かないけど、契約審査員ですか?」
![]() 「そうです。そういう立場なことも初めて知りました。
「そうです。そういう立場なことも初めて知りました。
そして驚いたのは、父はISO認証制度が、10年も続かないのではないかというのです」
![]() 「ほう〜、実は私も今の勢いは何年も続かないとは思っていた。なくなることはないだろうけど。
「ほう〜、実は私も今の勢いは何年も続かないとは思っていた。なくなることはないだろうけど。
しかしそれは、お父さんにとって深刻な問題ですね」
![]() 「いえ、年金がもらえるまであと7年くらいは、大丈夫だろうと笑っていました」
「いえ、年金がもらえるまであと7年くらいは、大丈夫だろうと笑っていました」
![]() 「なるほど。
「なるほど。
契約社員なら……早期退職とかして契約審査員になったのかな?」
![]() 「はい、大手の水処理会社に勤めていましたが、5年ほど前にリストラがあり技術士の資格を持っていたので、独立したらと甘い言葉で退職を勧められて辞めてしまったのです。街で技術士事務所なんて看板挙げても仕事なんてありません。独立するなら現役時代から手を打っておかないとダメですね。
「はい、大手の水処理会社に勤めていましたが、5年ほど前にリストラがあり技術士の資格を持っていたので、独立したらと甘い言葉で退職を勧められて辞めてしまったのです。街で技術士事務所なんて看板挙げても仕事なんてありません。独立するなら現役時代から手を打っておかないとダメですね。
それでISO9001の審査員の資格をとって、認証機関を訪問したのですが、正社員はとても無理で契約審査員になりました。それから2年になります。今はISO14001の審査員資格も取ったそうです。
契約審査員は月に10日くらいしか仕事がなく、ISOコンサルをする人が多いそうですが、父は口下手ですから……」
![]() 「分かった。まあ、記者になればいろんな人と会うからね、あまり感情的というか思い入れをしないようにしてください」
「分かった。まあ、記者になればいろんな人と会うからね、あまり感情的というか思い入れをしないようにしてください」
![]() 「はい、そのように努めます。
「はい、そのように努めます。
それで思ったことがあるのですが……お時間、よろしいですか?」
![]() 「どうぞ」
「どうぞ」
![]() 「父から言われたのですが、この雑誌の顧客をどう考えているのかというのです。
「父から言われたのですが、この雑誌の顧客をどう考えているのかというのです。
アイソムズ誌は明確に審査員が対象です。アイソス誌は広告では審査員から企業担当者までと書いてありますが、本を読むと企業担当者といってもマニアのような人向けでしょうね。一般の人には向いてないようです」
注:企業の人を対象とした「ISOマネジメント誌」は、この物語の時点より遅い2000年創刊だった。
![]() 「つまり一般企業の担当者とか、ISOに無関係な社員を対象にすべきということか?」
「つまり一般企業の担当者とか、ISOに無関係な社員を対象にすべきということか?」
![]() 「そうは言いません。ただはっきりさせるべきだと思いました。父の言葉で恐縮ですが、懇談会の記事も審査員側から見た風景と、企業側から見た風景は相当違うはずです。ですからどちらよりにするのか、そういうスタンスを明確にするべきと言っていました」
「そうは言いません。ただはっきりさせるべきだと思いました。父の言葉で恐縮ですが、懇談会の記事も審査員側から見た風景と、企業側から見た風景は相当違うはずです。ですからどちらよりにするのか、そういうスタンスを明確にするべきと言っていました」
![]() 「なるほど、参考にさせてもらう。こういうのは会社の方針だからね」
「なるほど、参考にさせてもらう。こういうのは会社の方針だからね」
今日は業界団体のISO研究会の幹部会だ。田中、金子、山口、中村が集まって話し合いをしている。
幹部会と言っても皆が幹部と選出したわけではない。暇な人が業界団体に来ることが多く、その人たちに「じゃあ頼むわ」ということになっただけだ。
今回は、先週の雑誌記者との懇談会の反省と、これからどういう方向で活動するかの打ち合わせである。
吉本さんが参加しようとしたが、田中が丁寧にお断りした。
| 金子 | ||||
| 田中 |  山口 山口 |
|||
先日の雑誌記者との懇談会は、研究会メンバーから好評価を受けた。記事になってもならなくても、外部の人に言いたいことを言ったことで気分を良くした。一般人から見れば、雑誌社の記者も立派なISOの関係者だ。話が伝わることを期待している。
押田さんが連れてきた若い記者が変なことを語っていたが、あんな奴の話はどうでもいいと思っている。
そして感じたのは、何ごとも証拠がないとダメだということだ。
「審査員に宴席を求められた」ではなく「いつ、どこで、どの認証機関のなんという審査員が宴席を求めた」でなければ証拠にならない。
不適合を議論するなら、所見報告書を見なくちゃならない。所見報告書のコピーを添付したいところだ。
それで審査トラブルのデータベースを作ろうという意見が盛り上がってきた。
知る限りの問題を考えるとそんなに複雑とは思えない。なぜなら問題は多々発生しているが、その種類は多くなく、せいぜい10パターンくらいしかない。規格解釈の問題と言っても、環境側面決定方法、環境マネジメントプログラムの構成くらいだ。
企業担当者から見れば、巷に溢れるISO規格解説本でしっかりとそういうことを解説すれば良かったのにと思う。環境側面の決定方法など、審査が始まってから大揉めに揉めている。自分たちが著した本の効果はごく狭い範囲に止まっている。
規格解説本は多数の人や認証機関が書いて発行されている。しかしどれも奥歯にものが挟まったような書き方で、要するに細かいことは書いてない。
こういう方法ですれば絶対揉めませんというのを見せてくれればよいのに。断定すると差しさわりがあるからか、モゴモゴとはっきり言わないのだ。
結局、解説本を書いた人も、規格要求の具体的な展開まで考えていないというか、知らないのだ。
研究会はなぜ具体的な細かいことまで書いたのかと言えば、佐川が前世の記憶から、どんなことがもめるか、間違えた解釈とはどんなものかを皆に説明したからである。それゆえ研究会が著した規格解説本が、内容的に突出していることは間違いない。
当初、5,000部出ればと考えていたが、既に再版、再再版となり1万2千部までいった。
印税は研究会メンバーの各社で申し合わせて、メンバーの取り分を半分とした。売価2,200円で12,000部で2,600万円。印税から勤め先の会社の取り分と認証機関の監修費用を引き、残りを10人で割ると、13万だ。臨時ボーナスと思えば、悪くはないだろう。業界の事務局担当者の![]() 吉本さんも、その中に
吉本さんも、その中に しっかり ちゃっかりと名を連ねている。まあ、名義代かハンコ代と諦めるしかない。
そして今計画している二冊目は、ISO14001審査トラブル対応本である。
メンバーはいろいろ思うところがあり、二作目には吉本さんを参加させないことにしたのだ。
![]() 「やはり対策を立てるには情報だね。各社の審査所見報告書を、全部集めることはできないだろうか?」
「やはり対策を立てるには情報だね。各社の審査所見報告書を、全部集めることはできないだろうか?」
![]() 「審査報告書は秘密でも何でもない。社外に公開しても特段問題はないですね」
「審査報告書は秘密でも何でもない。社外に公開しても特段問題はないですね」
注:審査契約で守秘義務を負うのは認証機関側だ。依頼する企業は守秘義務を負わない。
認証機関によって審査契約の中身が違うかもしれないからご確認してください。
また審査報告書は公開されることに問題がない。顧客によっては、審査登録証のコピーだけでなく審査報告書を要求するところもある。
![]() 「どこかの自治体がISO14001認証してウェブにアップしたら、評価された部分だけウェブにアップしたので、一部だけ公開するのはダメで、全文を公開しろと言われたことがあったはずだ」
「どこかの自治体がISO14001認証してウェブにアップしたら、評価された部分だけウェブにアップしたので、一部だけ公開するのはダメで、全文を公開しろと言われたことがあったはずだ」
![]() 「企業から見れば社外秘だろう。内容から見たら損益も技術も関係ない。不適合があると恥ずかしい思いはするだろうな」
「企業から見れば社外秘だろう。内容から見たら損益も技術も関係ない。不適合があると恥ずかしい思いはするだろうな」
![]() 「会社責の問題は対象外だろう。異議申し立てするものであれば会社の恥じゃない。いずれ匿名にするのだから説得できないものかな?」
「会社責の問題は対象外だろう。異議申し立てするものであれば会社の恥じゃない。いずれ匿名にするのだから説得できないものかな?」
![]() 「我々が複数の会社の事例を、マージしたり脚色したりするのはどうでしょう?」
「我々が複数の会社の事例を、マージしたり脚色したりするのはどうでしょう?」
![]() 「それが良さそうだ」
「それが良さそうだ」
・
・
・
・
![]() 「ある程度サンプルを集めて対応を示すとして、また監修が必要だろうな。我々だけで間違いないものは作れるだろうけど、お墨付きがないと売れ行きに関わる」
「ある程度サンプルを集めて対応を示すとして、また監修が必要だろうな。我々だけで間違いないものは作れるだろうけど、お墨付きがないと売れ行きに関わる」
![]() 「また、産業環境認証機関に頼むのか?」
「また、産業環境認証機関に頼むのか?」
![]() 「認証機関を替えてB○○社のハワードさんに頼むのもありかな?」
「認証機関を替えてB○○社のハワードさんに頼むのもありかな?」
![]() 「考えられるメリットは? デメリットは?」
「考えられるメリットは? デメリットは?」
![]() 「メリットは信頼性だね。監修者のイギリスでのBS7750審査経験も売りになるだろうし、産業環境よりは規格解釈のレベルは高いでしょう。
「メリットは信頼性だね。監修者のイギリスでのBS7750審査経験も売りになるだろうし、産業環境よりは規格解釈のレベルは高いでしょう。
デメリットは産業環境から憎まれるかな。まあ産業環境に義理立てすることもない。吉本さんがいないから反対する人もいないよ」
![]() 「分かった。編集が進めばメンバーで決定しよう。早めに見てもらったほうがスケジュールを詰めることができる」
「分かった。編集が進めばメンバーで決定しよう。早めに見てもらったほうがスケジュールを詰めることができる」
![]() 「世の中に出すのはそれで良いだろうけど、業界傘下の企業に対しては、認証機関の問題点や解釈の違いをまとめて広報すべきじゃないのかな?」
「世の中に出すのはそれで良いだろうけど、業界傘下の企業に対しては、認証機関の問題点や解釈の違いをまとめて広報すべきじゃないのかな?」
![]() 「それは……難しそうですね。というのは業界団体の研究会がそれをしたら、認証機関から苦情が来ませんか」
「それは……難しそうですね。というのは業界団体の研究会がそれをしたら、認証機関から苦情が来ませんか」
![]() 「今までの審査結果を評価してランキングを作ったとしても、それを傘下企業に伝えるか否かは、個々の企業で考えた方が良いでしょうね」
「今までの審査結果を評価してランキングを作ったとしても、それを傘下企業に伝えるか否かは、個々の企業で考えた方が良いでしょうね」
![]() 「それならその通知の責任は各親会社の責任ということで、業界団体とかの責任じゃないからな」
「それならその通知の責任は各親会社の責任ということで、業界団体とかの責任じゃないからな」
1週間が過ぎ、また週末になる。
増子宅である。今週、増子(父)は月火は無職だった。水木金の三日間は横浜の工場の審査で、日帰りしている。片道2時間弱かかるが、泊まるまではないと通勤している。
というわけで今日の夕食は、増子(子)が炊事して、父親が帰って来るのを待っている。
8時には帰って来るだろうと思っていると、案の定、7時過ぎに父親が帰宅した。
父親は食卓に並んだ料理を見て、息子も少しは家事ができるようになったかと安心する。
![]() 「お疲れ様です。まずはお風呂に入ってよ」
「お疲れ様です。まずはお風呂に入ってよ」
![]() 「いやはや、ごちそうだな。それじゃお言葉に甘えて、先に風呂を頂くわ」
「いやはや、ごちそうだな。それじゃお言葉に甘えて、先に風呂を頂くわ」
・
・
・
・
 |  |
お互い1週間の出来事を報告しあう。増子(父)が日帰りであっても、夕食を一緒にするのは土曜日だけだ。
増子(父)は、息子がISO認証の話ができるようになったのがうれしい。
![]() 「お父さん、ISO審査員って皆、環境に関わる仕事をしてきて、高齢になって第一線を外れた人が多いようだけど、新卒はいないの?」
「お父さん、ISO審査員って皆、環境に関わる仕事をしてきて、高齢になって第一線を外れた人が多いようだけど、新卒はいないの?」
![]() 「審査員になる要件があって、高卒で実務経験5年、短大以上は4年、そのうち2年は環境マネジメント分野の業務であることとなっている」
「審査員になる要件があって、高卒で実務経験5年、短大以上は4年、そのうち2年は環境マネジメント分野の業務であることとなっている」
![]() 「なるほど、じゃあ若い人とか実務経験のない人はダメなんだ。
「なるほど、じゃあ若い人とか実務経験のない人はダメなんだ。
でも環境マネジメント分野と言われても、そういう職に就いている人なんて少ないでしょう」
![]() 「学歴はともかく、実務経験といってもあまり厳密ではない。
大学院で環境投資
「学歴はともかく、実務経験といってもあまり厳密ではない。
大学院で環境投資
![]() 「なるほどなあ、
「なるほどなあ、
実は編集長の押田さんから、お父さんに聞いてほしいという宿題があるんだ」
![]() 「ワシのことを編集長に話したのか?」
「ワシのことを編集長に話したのか?」
![]() 「まずかった?」
「まずかった?」
![]() 「いや別に。あまり難しいのは分からんぞ。認証機関の経営などとは縁がない」
「いや別に。あまり難しいのは分からんぞ。認証機関の経営などとは縁がない」
![]() 「○○業界系のJ□□認証機関では、今年、大卒の女子を数人審査員候補として採用したそうです。環境は若さ、女性という切り口で売り込みを図る狙いだそうです。
「○○業界系のJ□□認証機関では、今年、大卒の女子を数人審査員候補として採用したそうです。環境は若さ、女性という切り口で売り込みを図る狙いだそうです。
その成功の見込みを知りたいと言います」
![]() 「その話は聞いたことがある。入社して三カ月か、審査員補ではなく審査員になったのかな。いや実務経験がないから、まだなれない。待てよ、4年も戦力にならないじゃないか」
「その話は聞いたことがある。入社して三カ月か、審査員補ではなく審査員になったのかな。いや実務経験がないから、まだなれない。待てよ、4年も戦力にならないじゃないか」
![]() 「まだ審査員にはなっていないようですね。4年間審査員ができないのも雇う方としてはロスですね」
「まだ審査員にはなっていないようですね。4年間審査員ができないのも雇う方としてはロスですね」
![]() 「好き勝手に言ってもいいんだろう。どうせわしの話なんて参考情報のひとつだろうし」
「好き勝手に言ってもいいんだろう。どうせわしの話なんて参考情報のひとつだろうし」
![]() 「好き勝手に言うなら、いろいろ考えることがあるわけね?」
「好き勝手に言うなら、いろいろ考えることがあるわけね?」
![]() 「そりゃ、あるさ。
「そりゃ、あるさ。
まず、そういう発想が、利害関係者に理解されているかということが問題だな」
![]() 「ちょっとメモさせてもらうね。
「ちょっとメモさせてもらうね。
利害関係者というと……社内で考えが理解されているということですか?」
![]() 「誤解されると困るから、録音しろ。ICレコーダーを持ってこい」
「誤解されると困るから、録音しろ。ICレコーダーを持ってこい」
息子が席を外して、ICレコーダーを持って来る。
![]() 「社内よりも出資者だな。J□□社は○○業界の7社が出資して作った認証機関だ。
「社内よりも出資者だな。J□□社は○○業界の7社が出資して作った認証機関だ。
出向者を含めて今社員の審査員は60数名いるはずだ。契約審査員は流動的だが50名はいるだろう。
前にも言っただろうが、社員審査員は人件費が高いから、少なくても同数近く契約審査員を置かないとペイしない。
そういう条件で新人を採用したら経営的にどういう問題があるか、康夫考えてみろ」
![]() 「考えてみろと言われても、想像するしかないよね。
「考えてみろと言われても、想像するしかないよね。
企業の引退間近な人なら新卒の2.5倍は取りますね。ですが出向者の場合、人件費の半分を負担すれば良い、となると出向者と新人の費用負担はそんなに変わらず、更に人件副費は認証機関負担では、これでは人件費を薄める効果はありませんね。
では女性であること、若い発想ができること、などが売り込みの効果があるかどうかですか」
![]() 「まあ30点だな。及第点にはほど遠い」
「まあ30点だな。及第点にはほど遠い」
![]() 「その口調では、若い女性を採用することは悪手と聞こえますね」
「その口調では、若い女性を採用することは悪手と聞こえますね」
![]() 「そもそも業界で認証機関を作るのは何のためか?」
「そもそも業界で認証機関を作るのは何のためか?」
![]() 「業界が審査を受ける費用を外に出さないことでしょうか」
「業界が審査を受ける費用を外に出さないことでしょうか」
![]() 「その通りだ。とはいえなんらかの制約条件がないなら、そういう発想は起きないだろう。
「その通りだ。とはいえなんらかの制約条件がないなら、そういう発想は起きないだろう。
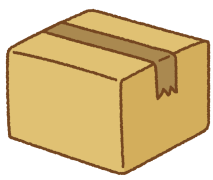 ほとんどの製品は段ボール箱に入っているが、段ボール製造……ええと紙パルプ製造業という業種かな、そういう仕事を社内に取り込むとか、子会社を作って事業化したり、業界で共同して段ボール会社を作ろうなんてとこはない
ほとんどの製品は段ボール箱に入っているが、段ボール製造……ええと紙パルプ製造業という業種かな、そういう仕事を社内に取り込むとか、子会社を作って事業化したり、業界で共同して段ボール会社を作ろうなんてとこはない
環境問題が起きる前は、梱包と言えば発泡スチロールだったが、発泡スチロールの成型作業を取り込んだところもほとんどなかった」
![]() 「なるほど、そう言われると確かに、
「なるほど、そう言われると確かに、
つまり本業以外に成形加工や梱包材などを内製化するには、技術、設備を用意するハードルが高くないことが必要だ。
その逆に、ものすごい付加価値がある作業なら内作取り込みをする」
![]() 「少しは頭が回るのだな。
「少しは頭が回るのだな。
そして内部に遊休人材がいて、その遊休人材を新事業に使えること、そういう条件があって初めて成り立つ」
![]() 「そこまでヒントをもらえたら先が見えました。
「そこまでヒントをもらえたら先が見えました。
認証機関が新卒を採用するには、出資企業に遊休人材がいない場合で、長期的にその事業を拡大していく方針である場合となります。
だって育成に4年もかかるのですから」
![]() 「まあ、そういうことだ。
「まあ、そういうことだ。
ワシの想像だが、あれは認証機関の社長の思い付きだと思うな。
新卒を3名採用したようだが、新卒を取らなければ出資企業から3名出向者を出せたわけだ。簡単に言えば余計な人を3名雇ってしまったわけだ。
お前んところの編集長の質問に答えるなら、新卒者を雇用するのは認証事業と無関係であり、経営的には稚拙としか言いようがない。
ワシが契約審査員の仕事が減ることを、心配しているわけじゃないぞ、アハハ」
![]() 「女性とか若い考えということで、認証ビジネスにメリットはないですか?」
「女性とか若い考えということで、認証ビジネスにメリットはないですか?」
![]() 「
元々、業界系認証機関とは、高い賃金をもらっている余分な人たちを、有効活用するのが目的だ。その目的と真逆の手を打っているのだからダメだ。
「
元々、業界系認証機関とは、高い賃金をもらっている余分な人たちを、有効活用するのが目的だ。その目的と真逆の手を打っているのだからダメだ。
仮にだ、若い女性に審査をしてもらいたいという企業があったとして、若い女性がいない場合に比べて絶対頼みたいという効果はないだろう」
![]() 「なんだか夢のない話ですね」
「なんだか夢のない話ですね」
![]() 「環境だといっても夢があるわけじゃない。
「環境だといっても夢があるわけじゃない。
そもそもISO14001規格の意図は何だか知っているか?」
![]() 「ISO14001の意図ですか?
「ISO14001の意図ですか?
未来に良い環境を残すとかですかね」
![]() 「そんなフワフワしたもんじゃない。『遵法と汚染の予防』だ。法違反をしない、事故を起こさないのが規格の意図だ。
「そんなフワフワしたもんじゃない。『遵法と汚染の予防』だ。法違反をしない、事故を起こさないのが規格の意図だ。
夢がないとは、地に足が付いているということだ」
![]() 「その伝ならISO9001の意図もあるのですか?」
「その伝ならISO9001の意図もあるのですか?」
![]() 「意図とは、目指すものとか目標だ、目的がなくて存在するものはない。
「意図とは、目指すものとか目標だ、目的がなくて存在するものはない。
ISO9001の意図は『顧客満足』だ」
![]() 「こちらはISO14001と違って夢というか前向きですね」
「こちらはISO14001と違って夢というか前向きですね」
![]() 「顧客満足の定義を知っているか?」
「顧客満足の定義を知っているか?」
![]() 「決して顧客に失望させないとか?」
「決して顧客に失望させないとか?」
![]() 「アホか! なこと不可能だ。顧客満足の定義は『顧客の要求事項が満たされている程度に関する顧客の受け止め方
「アホか! なこと不可能だ。顧客満足の定義は『顧客の要求事項が満たされている程度に関する顧客の受け止め方
言いたいのは顧客満足とは顧客の希望を完璧に満たすことではなく、どれくらい満足したかのレベルだ」
![]() 「考えてみれば完璧なんてありえませんね。どれくらい満足したかを測るのはまっとうでしょう。とはいえ何を指標にするのか見当もつきません」
「考えてみれば完璧なんてありえませんね。どれくらい満足したかを測るのはまっとうでしょう。とはいえ何を指標にするのか見当もつきません」
![]() 「まあ、それは考えるところだな」
「まあ、それは考えるところだな」
![]() 「考えるのは、審査を受ける人なのでしょうね」
「考えるのは、審査を受ける人なのでしょうね」
![]() 「そういうことだ。間違ってもISO審査員じゃない。審査員は楽だな。規格を作った人はもっと楽だ。
「そういうことだ。間違ってもISO審査員じゃない。審査員は楽だな。規格を作った人はもっと楽だ。
ところで大卒女子の採用を考えるのはもういいのか?」
![]() 「お父さん、ありがとう。見当もつかないところから、見通しが付くところまでは来た気がする。これはISO規格とか認証のことではなく、経営問題だね」
「お父さん、ありがとう。見当もつかないところから、見通しが付くところまでは来た気がする。これはISO規格とか認証のことではなく、経営問題だね」
![]() 「そう言っただろう。前回も話したと思うが、ISO認証が環境に貢献するとか、カッコいいなんてことは全くない。なにもないところで考えた濡れ手に粟の金儲けだよ。
「そう言っただろう。前回も話したと思うが、ISO認証が環境に貢献するとか、カッコいいなんてことは全くない。なにもないところで考えた濡れ手に粟の金儲けだよ。
そういうのをバブルというのじゃなかったかな?」
![]() 「バブルって経済が過熱することでしょう」
「バブルって経済が過熱することでしょう」
![]() 「バブルとは何百年も前からある概念だ。あるものが高く取引されるだろうという思惑から、実態以上の値が付くことだ。そしていつか化けの皮がはがれて価値がなくなり、バブルははじけるという定めだ。
「バブルとは何百年も前からある概念だ。あるものが高く取引されるだろうという思惑から、実態以上の値が付くことだ。そしていつか化けの皮がはがれて価値がなくなり、バブルははじけるという定めだ。
お前はチューリップバブルなんて知っているか?」
![]() 「チューリップはどうでも良いけど、なにもないところでって、どういう意味?」
「チューリップはどうでも良いけど、なにもないところでって、どういう意味?」
![]() 「ISO認証ってなにもないからさ。商品なら物、サービスなら床屋だって税理士だって存在意義のあるサービスだ。
「ISO認証ってなにもないからさ。商品なら物、サービスなら床屋だって税理士だって存在意義のあるサービスだ。
ISO認証って何を与えてくれるのか、考えたことあるか?」
![]() 「是非ともお聞きしたいですね」
「是非ともお聞きしたいですね」
![]() 「それは来週末まで取っておこう。その前にその……押田編集長に聞いてみろ。
「それは来週末まで取っておこう。その前にその……押田編集長に聞いてみろ。
ワシもその編集長の考えの深さを知りたいね」
某日、吉宗機械の社長室だ。
社長と執行役経営企画室長、執行役財務部長がテーブルを囲んでいる。
 奥田社長 | ||
 経営企画室 中山室長 |  |
![]() 「皆さんの努力でアジア通貨危機による損害はほとんどなく、それどころか300億の利益が見込めたか」
「皆さんの努力でアジア通貨危機による損害はほとんどなく、それどころか300億の利益が見込めたか」
![]() 「さようです。
「さようです。
多くの企業、特に東南アジアと取引が大きいとか、工場を作ったところは為替相場の急変化で大揺れです。当社は説明しましたようにその変動をプラスにしました。
未来プロジェクトの効果はすごいですね。これからも黙っていても年1,000億くらいの為替や株での投資効果、事故や危機からの回避が期待できます」
![]() 「中山さん、あなたはこの活用をどう考えている?」
「中山さん、あなたはこの活用をどう考えている?」
![]() 「未来プロジェクトはアジア通貨危機だけでなく、多面で成果を出しています。総会屋問題でも社会問題になる前に把握しましたので、緊急に内部監査を行いましたし、未来に報道された事から逆にたどって膿を出しました。
「未来プロジェクトはアジア通貨危機だけでなく、多面で成果を出しています。総会屋問題でも社会問題になる前に把握しましたので、緊急に内部監査を行いましたし、未来に報道された事から逆にたどって膿を出しました。
それで警察などが入る前に、自主的に対処し広報したことで大問題にならずに済みました。他社と違い、捜査が入る前に公表しましたから、他社ほどマスコミに叩かれていません。
結果、会社の評判も棄損せず、その効果はお金では言い表せません。
社長の懸念することも分かります。未来プロジェクトに頼り切るのは危険です。財務部では景気動向や危機を予測する力や資産運用の技術を失うかもしれません。
不祥事に関しても、
予言そのものも100発100中でないかもしれません。あるいはタイムマシンの小説によくあるように、ひとつを変えただけでも、その影響でそれ以降の出来事が変わってしまうかもしれない。
会社のルールとして参考にとどめるとか、他の方法がないときにのみ参照を許すとか制限を付けるべきでしょう」
![]() 「中山室長がおっしゃることに同意します。
「中山室長がおっしゃることに同意します。
今回はだいぶ前に情報を得られて検討する時間があり、為替の大変動があってもなくても、大損をしないことを目的としました」
![]() 「みなさんの努力に水を差すようだけど、私はね、こういう方法はフェアじゃないように思うのよ。神様が見ていたら罰を受けるかもしれないって気がする。
「みなさんの努力に水を差すようだけど、私はね、こういう方法はフェアじゃないように思うのよ。神様が見ていたら罰を受けるかもしれないって気がする。
完全に封印したら、どんな不具合がありますか?」
![]() 「完全に予言を参照しないのですか?
「完全に予言を参照しないのですか?
安全な道を歩めるのに……先が見えない闇の中を歩くのですか?」
![]() 「同業他社のS社がバブルのとき投資の事業部まで作って大々的にやっていたよね。もう7年位前かな。あそこは本業の利益より、投資の利益が大きいなんて言われていた。
「同業他社のS社がバブルのとき投資の事業部まで作って大々的にやっていたよね。もう7年位前かな。あそこは本業の利益より、投資の利益が大きいなんて言われていた。
バブル崩壊のとき、それによって大損害ということはなかったようだけど、ほぼ10年間、技術的な研究に力を入れず、それによって本業でどんどんと同業他社に後れを取り、今は中国に身売りするかって話だ」
![]() 「予言を利用して投資に力を入れることと、予言を活用してリスク低減を図ることは大違いと思いますが」
「予言を利用して投資に力を入れることと、予言を活用してリスク低減を図ることは大違いと思いますが」

![]() 「もちろん、その二つは違う。だけど勝ち馬の確実な情報を持っていたら、欲を出さないか。
「もちろん、その二つは違う。だけど勝ち馬の確実な情報を持っていたら、欲を出さないか。
予言に頼らず、先が見えない人間であるからこそ、その場その場で最善を尽くすのが正しい道に思えるんだが」
![]() 「社長のお話では、予言を活用して本業以外のビジネスをするのは反対だけど、本業において予言を活用して新製品開発とか特許をとることについては許されるように聞こえますが?」
「社長のお話では、予言を活用して本業以外のビジネスをするのは反対だけど、本業において予言を活用して新製品開発とか特許をとることについては許されるように聞こえますが?」
![]() 「言葉足らずだった。そういうのも控えなければならない気がする」
「言葉足らずだった。そういうのも控えなければならない気がする」
![]() 「時代はどんどん変わり、事業さえ乗り換えていかないと組織を維持できない時代です。従来からの本業に拘ることもないと思います。
「時代はどんどん変わり、事業さえ乗り換えていかないと組織を維持できない時代です。従来からの本業に拘ることもないと思います。
1990年頃の話ですが、アメリカのフォード社は30年後には自動車製造販売会社から、モビリティサービスを提供する会社に変わると言ったそうですね」
![]() 「それは、車を売るのではなく、カーシェアリングとかレンタカーなど全体の運用システムをイメージしていたのだろう。だけど現実は今フォードの中で一番利益を出しているのは自動車ローンというから、金貸しになってしまったようだ」
「それは、車を売るのではなく、カーシェアリングとかレンタカーなど全体の運用システムをイメージしていたのだろう。だけど現実は今フォードの中で一番利益を出しているのは自動車ローンというから、金貸しになってしまったようだ」
![]() 「IBMを見れば、大昔はタイプライターを作り、戦争中はライフル銃を作り、メインフレームを作り、ソフトウェアを作り、パソコンを作り、今はHDなどハードをすべて切り捨てて、ソリューションビジネスに移ったようです。
「IBMを見れば、大昔はタイプライターを作り、戦争中はライフル銃を作り、メインフレームを作り、ソフトウェアを作り、パソコンを作り、今はHDなどハードをすべて切り捨てて、ソリューションビジネスに移ったようです。
当社も先を読んで時代に遅れないようにしなければなりません。そのためのひとつの武器と考えられませんか」
![]() 「時代に合わせて企業が変身、変態は必定だろうけど、無節制にチートスキルを使うのはどうなんだろうなあ〜」
「時代に合わせて企業が変身、変態は必定だろうけど、無節制にチートスキルを使うのはどうなんだろうなあ〜」
![]() 「仮に未来プロジェクトからの情報提供がなかったなら、アジア通貨危機で当社は巨額の損を出し、これからどう立て直すか上を下への状態でしょう。それが良いとは思えません」
「仮に未来プロジェクトからの情報提供がなかったなら、アジア通貨危機で当社は巨額の損を出し、これからどう立て直すか上を下への状態でしょう。それが良いとは思えません」
![]() 「近い将来、コンピュータとソフトの進歩で我々の仕事がなくなるかもしれない。それと類似な気がしたのだが、人間が譲れないものがあるのではないかと思うのだ」
「近い将来、コンピュータとソフトの進歩で我々の仕事がなくなるかもしれない。それと類似な気がしたのだが、人間が譲れないものがあるのではないかと思うのだ」
![]() 「社長のお考えは分かりました。もう一度検討させてください」
「社長のお考えは分かりました。もう一度検討させてください」
 中山室長と後藤部長は社長室を出る。
中山室長と後藤部長は社長室を出る。
廊下を少し歩くと中山室長は、まっすぐ自職場に戻ろうとする後藤部長の肩をつかんで、親指で並んでいる会議室を指す。
黙ったまま二人はその一つに入る。
![]() 「どうしました」
「どうしました」
![]() 「社長も不安なんだろう。怪しげなものを使って上手く言っても、何故か分からないから気持ちが悪い」
「社長も不安なんだろう。怪しげなものを使って上手く言っても、何故か分からないから気持ちが悪い」
![]() 「まあ、確かに。何か説得する方法がありませんか?」
「まあ、確かに。何か説得する方法がありませんか?」
![]() 「私は予言者に社長を説得、いや説明してもらおうと考えているんだ」
「私は予言者に社長を説得、いや説明してもらおうと考えているんだ」
![]() 「予言者とは?」
「予言者とは?」
![]() 「あなたも私も頼った予言を語った男だよ」
「あなたも私も頼った予言を語った男だよ」
![]() 「予言を語ったって、あの予言は人間が語っているのですか?」
「予言を語ったって、あの予言は人間が語っているのですか?」
![]() 「人工知能がプリントアウトしたとでも思っていたの? それとも会社資料室に予言集でもあると思った?
「人工知能がプリントアウトしたとでも思っていたの? それとも会社資料室に予言集でもあると思った?
未来から戻ってきたという社員がいて、彼の語ることを試してみたらことごとく当たった。それで始まったのが未来プロジェクトさ」
![]() 「予言者なら社長を説得できますか?」
「予言者なら社長を説得できますか?」
![]() 「社長を説得できたかどうかの予言はない。でも何もしなきゃ変わらんでしょう」
「社長を説得できたかどうかの予言はない。でも何もしなきゃ変わらんでしょう」
![]() 本日の言い訳
本日の言い訳
今日は場面が多くしかも混ぜこぜで、ワケワカランなんて言わないでください。
書き方を、いろいろトライしてみます。
最後のシーンですが、元々の構想では社長の鶴の一声で、未来プロジェクトは解消される予定でしたが、どうしたら良いですかね。
未来を知っているチート(ずる)を活用するのは道徳的にマズイという理屈もありそうです。でもインチキできないなら、タイムスリップする意味がありません。
実際にこんな事態になれば、会社トップの多くは未来プロジェクト中止を命じるかなと思いますが、どうでしょう?
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
ESG投資とは企業の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取り組みを評価して投資対象を選ぶ投資手法のこと。 流れとしては、1970年代からSRI(倫理投資)があり、1990年代にはグリーンファンド(環境投資)に進み、2000年代にCSR(社会的責任投資)となり2006年頃からESG投資と発展した。 しかし現実世界はウクライナ侵攻によってエネルギー危機が起こり、またグリーンウオッシュなど詐欺もあり、世界的にブームは終わったようだ。 2020年以降「ESGは当たり前」となり、ESGが大義名分となる時代は終わったようだ。 | |
| 注2 |
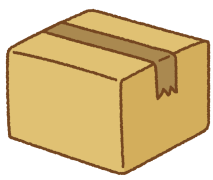 社内で段ボール箱を内製している会社もなくはないが、特殊なものだけだ。大企業であってもほとんどが、段ボール製造はレンゴーや王子HDなどの専業メーカーから調達している。
社内で段ボール箱を内製している会社もなくはないが、特殊なものだけだ。大企業であってもほとんどが、段ボール製造はレンゴーや王子HDなどの専業メーカーから調達している。内製しているのは飲料品メーカーなどがあるが、それも板紙を印刷して箱にしているだけで、板紙は購入しているところがほとんどである。 段ボール製造は装置産業であり、工場一つで使用する段ボール箱くらいを作ってもペイしない。 | |
| 注3 |
正しく言えばこの時点で品質用語の定義集であるISO8402:1994では定義されていない。ISO8402:2000で「顧客の要求事項が満たされている程度に関する顧客の受け止め方」と定義された。その後ISO8402:2008も同じである。 2015年改定で品質用語の定義がISO9000:2015に変わり、そこでの定義は「顧客の期待が満たされている程度に関する顧客の受け止め方」と、requirementsからexpectationsに替わった。要求から期待へとレベルアップしたのだろう。 |
外資社員様様からお便りを頂きました(25.07.03)
吉宗機械の社長室 によせて おばQさま 今回の社長室のお話良かったですね。 経営の立場から見れば、未来予測は「可能性の一つ」でしかない。 だから、まともな経営者ならば、リスク管理として利用するのが当然です。 裏返せば、成功出来ると信じて賭けに出る経営者は危険すぎる。 だから未来予測が危険だと考える社長は、まともな経営者。 歴史で言えば、信長の偉いのは桶狭間では劣勢の中で賭けに出たが、以降は極力勝てる条件の中でしか開戦しなかったから。 だから、未来予測できる人間が転移してきても、決断の補強と見るだけで、それで勝ちを確信しないはず(味方の鼓舞は別) 関ケ原でも、小早川の裏切りは予測の範囲だったが対抗の朽木、赤沢まで裏切るとは予想できなかった。つまりリスク管理の失敗。 一番の問題は、西軍大将の毛利が受動的で、輝元が大阪城で遊軍になり現地をマネジメントできていなかった。 この時点で勝てる体制でないと見切れなかったのが三成の限界。 だから未来予測があれば、あの時点で開戦しないのが最善で、大阪城から輝元、可能ならば秀頼を連れてこない限り勝てないと考えるのが最善。 ミッドウェーの南雲司令だったら、空母が出て来ている可能性を排除せず雷装の飛行機は2−3割残し、十分な索敵を継続し死角を無くすという当たり前のリスク管理継続するだけ。もし転移者の「たわごと」を信じて、発見していない空母への攻撃に全てをかけたとしたら指揮官失格でしょう。 現実では「空母はいない」「島を占領出来る」という希望的観測を信じて、作戦に確証バイアスを持ったから負けるべくして負けた。 歴史を未来の知恵からひっくり返す小説は多いですが、多くはムリがあるのは当然。 だって未来予測があるのに、戦わないとか正攻法なんて結論が出ても面白くないからですね。 |
外資社員様 毎度ありがとうございます。 物事は大局を見ることもあり、局地だけを考えることもあります。また自分の体験から考えることと、他人の経験から学ぶこともできます。 佐川が30年前に戻ったとき、前回と同じに生きるのではなく、流れにあらがって自分の考える正義を成そうとするのは、後悔を取り消すという意味で、自然な生き方かと思います。前回、副工場長にイジメられて辛かったが今回も同じ流れだとか、前回、目の前で女性が大怪我をしたのにまた傍観するという選択はないと思います。 では、アジア通貨危機があると知っている人が、手を打たずその場で右往左往すべきか、予め手を打っておくかとなると情報は最大限に活用すべしという発想は罪ではないと思うのです。 となると決断に迷う理由は、未来から帰ってきた本人か、それを聞いた人の違いだけになります。 その信頼性はどうかとなれば、たくさんの予言が成就したか・しなかったか調査して、参考にする重要度を決定するというのが落としどころかと思います。 社長はまだどれくらいの打率か知らない状態です。しかし灰皿事件から見ていた人がいたら、その情報は十分参考に値すると思います。 となると大いに活用すべしという結論もおかしくない。 でもって社長の周りの人が、佐川の打率を知っているなら、社長を説得するべきと思います。 佐川の立場なら、経営には無縁で雲の上の人に意見する気もないでしょうから、採用しないのも経営方針だと思うだけで終わると思います。 特許とか商標などはバンバンとっていて、罰は当たらないかと思います。iPhone、iPadなどは金になったと思うのですけど。 |
外資社員様からお便りを頂きました(25.07.04)
おばQさま お相手有難うございます。 >iPhone、iPadなどは金になったと思うのですけど。 iphonビジネスの独自開発は、日本企業では技術的に無理なので、FOXCONNのように下請けで製造引き受けなら可能性ありですね。 ただ、この時代から日本企業は海外製造にシフトするから、それを止められればですが。 |
外資社員様 毎度ありがとうございます。 私の言葉足らずでした。 私の意図は「iPhone、iPadなどを 商標登録をしておけば 金になったと思う」ということです。技術的な意味合いは全くありません。 昔iMacがありましたが、Appleは「i」で始まるのが好きなようで、iPhone、iPad、iPod touch、iBookなどがあります。 1997年頃に、こういったものを国内だけでも商標登録しておけばと思います。 ちなみに「アイホン」というインターフォンを作っている会社がありますが、Appleはスマホに限って「iPhone」を使えるようお金を払って契約したと聞きます。 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |