注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
 「ISO認証誌」の11月号に「有益な環境側面はISO14001の神髄(111話)」を寄稿した青木は、その後何度も、押田編集長に反響を問い合わせていた。
「ISO認証誌」の11月号に「有益な環境側面はISO14001の神髄(111話)」を寄稿した青木は、その後何度も、押田編集長に反響を問い合わせていた。
佐川の反論が待ち遠しいのだ。
青木はなぜか、会ったこともない佐川を敵視している。
11月号が発行されてすぐに、押田編集長から、青木の文に大量の反論が寄せられていることが伝えられた(第111話)。そして佐川に青木説に反論あれば、掲載する旨を伝えたと返事があった。
12月号の発売の1週間ほど前に、押田編集長から、佐川ではなく、彼が属している環境ISO研究会の寄稿が載るとメールがあった。
メールには、著者は佐川でなく環境ISO研究会であること、内容も青木への反論ではなく有益な環境側面がないことの解説だと、くどいほど注意があった。
青木は12月号の発売日に購入して、早速「俺にも言わせろ」のページを開いた。
「有益な環境側面があると語る審査員やコンサルがいることを憂い(113話)」なんて表現には、たまげない。論敵へのエール交換のようなものだ。
だが読み進めると肩が震えてくる。確かにそれは青木の論の否定ではない。だが有益な環境側面の全否定である。裏読みするとISO規格の否定とさえ受け取れる。
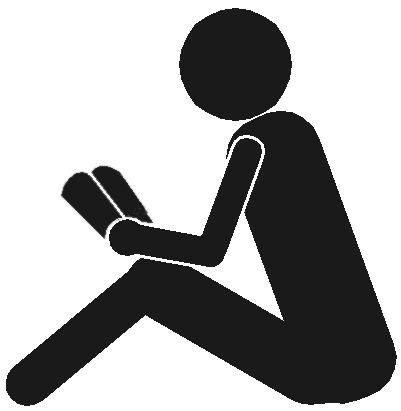 |
|
| 奴は何を語っているのか |
佐川の論は・・・研究会の見解とされているが、実質は佐川なのだろう・・・彼はISO規格を単なる道具と思っている。それも素晴らしい道具ではなく、いやいやながら使っているような感じだ。
彼にとってISO14001はなくても良い物、ISO認証はない方が良い物らしい。
ISO規格を神の声、金科玉条、無謬のものと考えている青木は、それに反感を持つのは当然だが、同時にその考えが理解不能である。
しかし読むにつれ佐川・・・と青木は思っている・・・の考えは、一貫して
もちろん青木は、ISO規格に「有益な環境側面」の文字がないのを知っているし、外国では有益な環境側面という表現がないのも聞いていた。
だが、だからこそ日本のISO14001はその上を行くのだ、それはISO審査を通じて、指導していくという考えである。
だが佐川・・・と青木は思っている・・・は、ISO審査とはコンサルではないとバッサリと切り捨てる。もちろんその根拠も示している。
一方、青木は、ISO審査は企業を指導するものと確信している。それはコンサルをしている者ならありがちだ。なぜならコンサルは改善が仕事だ。
もっともISOコンサルなら、認証すればそれでヨシとも言えるが・・・
反面、企業でISOに関わった者は、ISO認証は企業がISO規格要求を満たす証明(裏書)としか見ていない者が多い。
それも青木は気に入らない。
注:上の文で、コンサルは「ISO審査」で、企業は「ISO認証」と異なるが理由はある。指導するのは「審査」の場であり、企業が欲するのは「ISO認証」であるからだ。
そこがズレの始まりとも言える。
もちろん審査のルールであるGuide62では審査でのコンサルを禁じているのは事実である。それはISO認証を企業の「仕組みの検証」であると考えているからだ。いやそれが認証の本来の目的なのだ
それにしても取り上げた事例は、青木が見ても問題ばかりだ。
不法投棄を有害な環境側面と説明した書籍を青木も読んだことがある。どう考えても、法に則った廃棄物処理が有益な環境側面で、不法投棄が有害な環境側面とは理屈に合わない。そもそも、いずれも環境側面でないことは明らかだ。
それって法を守れば、有害な環境側面はなくなるのか? 法が改正されると、有益と有害は変わるのか? 矛盾だらけだ。
ましてや、有益な環境
程度の低い有益な環境側面を語る連中を、排除したい。

しかしと、青木は考える。
有益な環境側面を主張するなら、自分の考える有益な環境側面を、しっかりと定義しなければならない。
環境影響と環境側面を混同するとは、環境影響や環境側面の定義さえ理解していないのだろう。
そういった者と、青木が同一視されたことに怒りが沸き起こる。
もっとも有益な環境側面をそう語っている人に対して、青木はそれに反論したことはない。佐川の文を読んで、そういった有益な環境側面論を問題と思うなら、以前から己の有益な環境側面論を守るために批判すべきではなかったのか?
それは有益な環境側面を語る人は同志ではなくても、有益な環境側面を語る人が多い方が良いと、心の中にあったのではなかろうか?
ならば有益な環境側面があるという多数説に向かって「有益な環境側面はない」と叫ぶのは勇者ではないか?
青木は他の怪しげな有益な環境側面説とは違うことを明示して、佐川に反論すると同時に、おかしな有益な環境側面を語る人を批判すべきではないのか。なぜそれをしないのか?
青木の有益な環境側面論を、佐川は「ゲートから出る有益な環境影響が有害な環境影響より多ければ有益な環境側面、その逆を有害な環境側面とする人たち」と呼ぶ。
その通り青木は11月号に書いている。
それを佐川・・・と青木は信じている・・・は、物やサービスが持つ社会に与える影響は環境影響ばかりではないこと、更に環境影響同士でもコンフリクトがある。だから環境の範囲だけとらえて、その影響を評価してはいけないと語る。
確かにそれに反論しにくい。まず青木は、エアコンのフロンによるオゾン層破壊と省エネの比較が必要という考えを聞いた覚えがある。
それはオゾン層破壊を止めるのか、地球温暖化を止めるのかという問題になる。要するに物事は単純ではないのだ。
PCBやカドミウムが規制後も、例外を設けて使用を続けていたとは知らなかった。青木が社会で働き始めた頃、カドミメッキのネジなど普通に使われていた。カドミメッキは錆びなくて良かったのにと思ったものだ。その後、亜鉛クロメートも規制されて不満に思った。
ともかく佐川の論に、脊髄反射的に今すぐ反論するのは止めた方がよさそうだ。少し考えよう。
それと有益な環境側面があると言っても、その理屈は多種多様だ。あまりレベルの低い人と共闘しても、良いことはない。

青木は、有益な環境側面を論じることは複雑なことだと理解した。青木の考えた範囲は狭かったのだ。
そう気づいてISO認証誌を机に放り投げる。そしてコーヒーを淹れようと立ち上がった。
 久保は今年の8月に、ISO認証誌が主催したディベート大会に参加して、そこで佐川に会った(109話)。
久保は今年の8月に、ISO認証誌が主催したディベート大会に参加して、そこで佐川に会った(109話)。
久保は毎月、ISO認証誌を定期購読している。帰宅してすぐに郵送されてきたISO認証誌を見て、夕食を終えるとすぐに手にした。
まず目次を見る。「俺にも言わせろ」と「ISO徒然草」の二つの連載は真っ先に見る。
12月号の「俺にも言わせろ」は、有益な環境側面はないと解説している。寄稿者がISO研究会となっているが、少し読むと、この著者は佐川だろうと思いつつ見開き2ページを読む。
ISO認証誌に載せるために、いろいろ考えたのだろう。有益な環境側面を網羅的にとらえているし、その種類も分けて分析している。立派としか言いようがない。
彼は本社でグループ企業のISO認証の指導をしていると語っていたが、確かに大局的であるだけでなく、ビジョンを持っている。全社をどこに導いていくかを、しっかり考えている。持っている裁量も極めて大きいのだろう。
歳を取り設計で使えなくなったからと、技術管理部門に移り文書管理をしている自分とは見ている視野が違う。書いているスタンスが日々のトラブル対応とかでなく、まさに環境マネジメントであるのが分かる。
ISO規格を読んで理解できないと、コンサルや審査員が書いた本を読んで学んでいる自分とは大違いだ。そんな人の発言に異議を付けたのが間違いとも言えるが、我が身のほどを知ったのは彼のおかげだ。
クヨクヨすることはない。これを励みに頑張るしかない。
振り返れば、自分がISOのプロになってもあまり意味はない。そうなっても活躍する場はない。仕事である文書管理でも、勉強すべきことは多々あるし、業務改善すべきことも多い。
自分がすべきことは、ISO規格を理解することより、本務を良く知り、改善をすることだろう。
佐川がISO認証制度は、あと20年続けば儲けものと言っていた。ISO認証より文書管理がサスティナブルなのは間違いない。自分は文書管理を究めよう。
ISO認証誌の出版社である。
中岡社長と、押田編集長、増子が集まって話をしている。
 |  |  |
||
| 押田編集長 | 中岡社長 | 増子 |
![]() 「毎月、自分ところの雑誌は読んでいるが、12月号の『俺にも言わせろ』は読み応えがある。これを読んで、噛みついてくる審査員や認証機関もあるだろうな。
「毎月、自分ところの雑誌は読んでいるが、12月号の『俺にも言わせろ』は読み応えがある。これを読んで、噛みついてくる審査員や認証機関もあるだろうな。
なにしろ、今、ISO14001の流行は有益な環境側面だ。それを否定されたんではお困りだろう」
![]() 「我々は悪く言えばコバンザメ商売ですから、宿主が倒れてしまうのは困ります」
「我々は悪く言えばコバンザメ商売ですから、宿主が倒れてしまうのは困ります」
![]() 「何を言っている、日本のISO14001がおかしくなれば、それこそオマンマの食い上げだ。そうならないように、我々がISO業界を誘導しないと」
「何を言っている、日本のISO14001がおかしくなれば、それこそオマンマの食い上げだ。そうならないように、我々がISO業界を誘導しないと」
![]() 「社長は何か良いアイデアをお持ちですか?」
「社長は何か良いアイデアをお持ちですか?」
![]() 「それを考えさせるために、お前たちを雇っているわけだが・・・案がないわけではない。
「それを考えさせるために、お前たちを雇っているわけだが・・・案がないわけではない。
一番簡単なのは、有益な環境側面がある派とない派で、討論させることかな」
![]() 「それは8月にやりました」
「それは8月にやりました」
![]() 「あれは真剣勝負ではなくスパーリングだ。
「あれは真剣勝負ではなくスパーリングだ。
真剣勝負すると問題か?」
![]() 「会社員の方は負けても痛まないでしょうけど、認証機関とか審査員なら負ければダメージは大きいでしょう。商売に絡みますから」
「会社員の方は負けても痛まないでしょうけど、認証機関とか審査員なら負ければダメージは大きいでしょう。商売に絡みますから」
![]() 「有益な環境側面が本当にあるなら、討論すれば勝つだろう」
「有益な環境側面が本当にあるなら、討論すれば勝つだろう」
![]() 「12月号で、有害な環境側面ない派は、有益な環境側面ある派を包囲しちゃいました。もう逃げ場がありません」
「12月号で、有害な環境側面ない派は、有益な環境側面ある派を包囲しちゃいました。もう逃げ場がありません」
![]() 「じゃあ白旗をあげるしかない」
「じゃあ白旗をあげるしかない」
![]() 「社長はそれではオマンマの食い上げになると言ったじゃないですか」
「社長はそれではオマンマの食い上げになると言ったじゃないですか」
![]() 「奇をてらったキャッチフレーズなど言わず、地道な審査をすれば良いだけだろう」
「奇をてらったキャッチフレーズなど言わず、地道な審査をすれば良いだけだろう」

![]() 「当社としては今後これに関して、どういう方向で行きますか?」
「当社としては今後これに関して、どういう方向で行きますか?」
![]() 「ISO認証体制がどういう見解を出すかだろう。
「ISO認証体制がどういう見解を出すかだろう。
我々の役目は、どちらが正しいか決めることではない。討論する場を提供したり、情報を提供することだ。
押田よ、佐川氏と増子父の対談を計画してくれ。面白い話になるんじゃないか」
![]() 「社長、それはお勧めできません」
「社長、それはお勧めできません」
![]() 「ほう、どうして?」
「ほう、どうして?」
![]() 「父も毎月、『ISO認証誌』を読んでいますが、その意見は佐川さんと同じです。ですからどちらが言い出しても相手はそれに同意するだけで、議論になりません」
「父も毎月、『ISO認証誌』を読んでいますが、その意見は佐川さんと同じです。ですからどちらが言い出しても相手はそれに同意するだけで、議論になりません」
![]() 「では二人の見解が異なる要求事項を見つけろ。
「では二人の見解が異なる要求事項を見つけろ。
二人に討論させればスパーリングでない真剣勝負になって、どちらかが負ける。それでこそ討論というものだ」
![]() 「考えます」
「考えます」
![]() 「まあ、有益な環境側面はほぼ決着がついたと思う。
「まあ、有益な環境側面はほぼ決着がついたと思う。
問題は、なぜ規格にない要求事項を思いついたのか、多くの人がそれを是としたのか、審査で不適合を出されてもその判断に従ったのか、それを究明しないとまた同じ問題、つまり存在しない要求事項が一人歩きするようになる。
ISO規格はcorrection(処置/不具合の除去)だけでなく、corrective action(是正処置/再発防止)を要求しているんじゃないか。
あのさ、手足を失っても、失った足や指が痛むのをghost pain(幻肢痛)というそうだ。この問題をghost requirement(幻の要求事項)と名付けて特集でも組めよ」
![]() 「それは面白そうですね」
「それは面白そうですね」
![]() 「お前たちがアイデアを出さないから、俺が代わりに頭を絞っているんだ」
「お前たちがアイデアを出さないから、俺が代わりに頭を絞っているんだ」
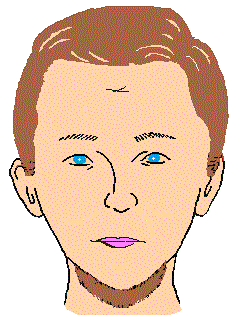 B〇〇社の神戸事務所である。日本事務所のボス、ハワードは優雅に午後の紅茶を飲んでいる。
B〇〇社の神戸事務所である。日本事務所のボス、ハワードは優雅に午後の紅茶を飲んでいる。
手にしているのは、以前、取材(半分宣伝である)を受けたお返しと、義理で購読している「ISO認証誌」である。
たぶん佐川が書いたのであろう「有益な環境側面はない」という記事を読み終えて、頭の後ろで手を組んで考える。
まず思うのは、この文章の存在意義である。自分なら規格を読んで、書いてある通りに、審査をする。
環境側面については、有益な環境影響も有害な環境影響も漏らさないように調べているか? 著しい環境側面を抽出する手順は決めているか? それは妥当なものか? 人が変わっても結果が変わることはないか?
そんなところだろう。
規格にに有益な環境側面とか有害な環境側面という言葉はない。なんでわざわざない物を作り出して、余計なことをしているのか。
なぜ日本人は無駄なことをするのか?
あげくにそれを否定し正すことが、この文の存在意義なのだ。素直に規格を読んで審査していたならまったく不要で、本来は存在しえない文章なのだ。
まったくおかしいとしか思えない。
免許持っている人が左側通行を知らないはずはない。
ならば右側通行が悪いこと、犯罪であることを広報するような、おかしなことではないのか?
おかしいことが当たり前になっていることを、おかしいと思わないのがより深い罪だ。
注:イギリスは日本と同じく左側通行です。
前月号で「ISO審査は改善の指導だ」と、お門違いなことを語っていたコンサルがいたが、なぜ認証制度、つまり認定機関とか認証機関の団体は、そういう意見を否定し排除しないのか?
 もっとも認証機関をあげて、有益な環境側面論を流行らせているところもあるようだが・・・
もっとも認証機関をあげて、有益な環境側面論を流行らせているところもあるようだが・・・
規格の誤った理解や不適切な審査は、ISO第三者認証制度を崩壊させてしまう。
そもそも有益な環境側面論の存在が、認証の信頼性の棄損だと知らないのか。
このような解釈をする低品質な認証機関の存在が、ハワードのB〇〇社にメリットがあるかとなると、そうならず、全体的にISO認証の価値を下げる結果となるだろう。
この記事がもたらす影響は、おかしな考えの認証機関や審査員の目を覚まさせるより、今まで無関心だった人たちが、ISO認証なんてくだらないと思わせる方が大きいのではなかろうか。
佐川も、こんな長文を書くことなく「ちゃんと英文を読め」と一行で済む話なのだ。
済まないから書いているのだろうが・・・・・・それは母国語が英語でないことばかりではなく、なにごとも改善につなげようとする匠の心かとハワードは笑った。
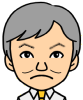 ここはJ△△認証である。
ここはJ△△認証である。
藤田部長はISO認証誌を手にして考えている。
あれはいつだったろう? H社の弁護士が当社の審査に苦情を言ってきたのは(104話)?
まだコートを着ていたから今年の春先、2月か3月だろう。
H社の工場の審査で有益な環境側面がないことで不適合を出したことに、H社・本社の法務部がいちゃもんを付けてきた。
環境のISO審査に法務部が異議を唱えるとはお門違いも甚だしいと思ったが、後で知ったがイギリスではISO規格の理解は弁護士が一番と言われているそうだ。
ともかく聞いてみれば異議が正しく、受け入れざるを得ない。幸い正式な異議申し立てでなかったので、当社が異議を受けた記録に残さずに済んだ。
しかしISO審査に法務部が異議を付けてきたことに驚いた。審査が民法に関わると思いもしなかった
もっとも以前、ウチのISO講習会のテキストに「著作者人格権は放棄しない
審査契約書も、ウチに出向する前に営業をしていた程度の人ではダメだ、弁護士に見てもらわないといいかんな。
ともかくあれ以降は、有益な環境側面がなくても良いというか、見ない振りをしろと言っている。
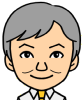 その他にも、審査員たちから環境マネジメントプログラムがふたつ無くても良いのかと言われて、散々揉めたが、今まで審査したところとの兼ね合いもあり、どうするか決めかねている。
その他にも、審査員たちから環境マネジメントプログラムがふたつ無くても良いのかと言われて、散々揉めたが、今まで審査したところとの兼ね合いもあり、どうするか決めかねている。
統一見解をしっかり作成して全審査員に周知徹底が必要だ。その前にその統一見解だが、どうしようか? 悔しいが他の認証機関に聞いてみようか。

正直言って、自分ほどISO14001を理解している者はおらんだろう、ISOTC委員を含めてだ・・・・・・そう思いながらパラパラと流し見ていく。
「俺にも言わせろ」のところに来た。11月号(111話)はイナカッペの跳ね上がりが、有益な環境側面のすばらしさを書いていた。
あれを読むと、有益な環境側面の発案者が私であると知らないようだ。
西東先生は自分の記憶を無意識に改竄しているようだ
初めはニコニコと読んでいたのだが・・・・・・しかし読む進むうちに顔色が変わって来る。
なんと、こいつは有益な環境側面などないと言うではないか・・・
なになに、有益な環境側面を語る人は多いが、人によって語る有益な環境側面はいろいろある、環境影響の原因全てが側面ではない・・・確かにそうだな。機械の故障や作業ミスは環境側面ではない。
ええと、改善活動を有益な環境側面だと考えているって・・・そりゃ勘違いだ。
アチャー、環境影響と環境側面を混同しているって・・・それってワシじゃないか!
何々、環境側面には有益も有害もないのか、こいつの言うことは間違いないようだ。
これじゃ、ワシは完璧な勘違い男になってしまう。有益な環境影響を書いた本には「有益な環境影響を有益な環境側面と言います」と書いていたが、あれは間違いだったか。
いや、待てよ。あれはどういう経緯だったろうか?
最初、ワシは有益な環境影響を忘れるなと講演で語っていたはずだが・・・・・・聴講者が有益な環境影響を有益な環境側面と言い出して、いつしかワシもそれに染まってしまったような気がする。
せめて「有益な環境影響を有益な環境側面と言っても良いでしょう」と書いておけば良かった。(それでも違うだろう)
だが、覆水盆に返らず、一度吐いた唾は呑めない。
問題は私の名声が・・・、既に出版した書籍はごまかしできない負の遺産だ。
困ったぞ、困ったぞ
 |
 |
||||
 | 困ったぞ、 間違いが 末代まで残ってしまう | 鏡に映る己の姿を見て脂汗を・・ |
西東先生は、鏡の前のガマのように、ダラ〜リ、ダラ〜リではなく、冷や汗をドバドバと垂れ流すのでありました
いえ、これはひどい言いぐさじゃありません。ありもしない亡霊、有益な環境側面を大々的に広めた西東先生は、一生その罪を負って生きてください。
もっとも三日もすれば忘れているか・・・面の皮が厚いだろうから
私のところに審査に来た審査員は「権威である西東先生(仮名)もおっしゃってますが、有益な環境側面を把握していないとダメです」と不適合を出していった。
権威とか関係ない、正しいか否かなんだよ!
似たようなものに
あなたたちがISO14001を貶めたんだ、しっかりと罪を償ってほしい。
考えてみれば、環境目的は3年とか、スコアリング法にあらずば不適合なんていろいろあったね、ヤレヤレ
とはいえ、朱鷺先生(仮名)も西東先生(仮名)も、とうに引退して悠々自適、ISO審査員時代のうそっぱちは、きれいさっぱり忘れているだろうな、
私も引退した身、しがらみなく仇敵を叩いております。
ところで、人間は他人から間違いを指摘されたら、素直にそれを認めるものでしょうか?
私自身も含めて、絶対にありませんね。人間はそれほど理性的ではないと思います。
二つの環境マネジメントプログラムが必要と主張していた朱鷺先生(仮名)が、「環境マネジメントプログラムはひとつでも良いのだ」多くの人から反論を受けたとき、ああだこうだと言って認めなかったことは歴史に残っています。
まあ、これはお話ですし、悪人を作らないのは私のモットーですから。
![]() 本日若干の釈明
本日若干の釈明
「俺にも言わせろ」のレベルが低いと思う方がいるかもしれない。
要旨は間違っていないと思うが、証拠とか論理立てなどに穴があるかもしれない。なにしろ私がチャチャと書いているから、校正さえ満足でない。
だけど、かってのアイソス誌とかISOマネジメント誌だって、論文の三要件
一般の審査員とかコンサルの書く文章は、論文のようにレビューをしっかりしてないし、裏をとってないものも多かった。
そういや、審査所見報告書だって、主語述語が合わないとか読解不可能なものもたくさんあった。
審査所見報告書をパソコンで書くようになると、マクロを組んで主要な言葉を入れるだけになり、文字は活字で美麗になったが意味不明は増えた。
ところで修士論文はA4で100ページもあれば十分らしい。仮に100ページ、1ページ1,000字とすると、論文の文字数は10万字、ものすごいと思うかもしれない。
だが、ちょっと待ってほしい(朝日新聞の常套句)
私の1話はミニマムで6,000字、長いものは13,000字くらいで平均9,000字はあるだろう。ちなみに本日のお話は、本文だけで8,8600字である。
となると10万字と言っても、私のお話の11話分、5週間で修士論文の
まあ、あまり仕上りレベルは求めないでください。
| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |
| 注1 |
ISO/IAF共同コミュニケ参照 | |
| 注2 |
提供されたサービスが 契約内容と異なる、提供の仕方が 契約で予定されていた水準に達していない場合、民法第415条の「債務不履行」として、損害賠償請求や契約解除ができる。 | |
| 注3 |
著作権は著作物を活用して収益を得ることができる財産的権利(著作財産権)と、著作者の氏名を表現する人格的権利(著作者人格権)がある。著作者財産権は譲渡できるが、著作者人格権はベルヌ条約で譲渡できない。つまり著作者人格権は放棄しないと書くのは何も知らんでかっこつけているだけ。 これは実際に某認証機関の審査契約書の中にあった。お節介な私はおかしいから直しなさいとわざわざ言った。もう当時の人は皆お亡くなりになったでしょうから苦情はこないでしょう。本当はまだ生きている(笑) 小説の版権を買うことはできるが作者と書くことはできない。特許権を買っても発明者にはならない。 ゴーストライターは氏名表示権の放棄でなく、氏名表示権を行使しないことと作者であると公表しない守秘義務契約をするそうだ。とはいえ多くの有名人(政治家・実業家・スポーツ選手・芸能人)の著作物は主人公名で出版されているそうだ。 枕草子の「くらげのななり」のように、権力者と言えど「お前のものはワシのもの」なんて許されません。 | |
| 注4 |
私の子供の頃、テレビでガマの油売りを演じるのをよく見かけた。 ・「筑波山ガマの油売り口上」解説 ・U-tubeより「筑波山ガマの油売り口上」動画 | |
| 注5 |
「われはわが咎を知る。我が罪は常に我が前にあり」は、夏目漱石の小説「三四郎」の登場人物の美禰子のセリフで、元々は旧約聖書の詩編51篇にあるダビデの言葉です。 但し、私の持っている1955年改訳(口語訳聖書と呼ばれるもの)では 「私は自分の咎を知っています。私の罪はいつも私の前にあります」 となっている。夏目漱石のセリフと違いカッコ悪い。 | |
| 注6 |
学術論文の三要件とは、 (1) 新規性:論文の内容に著者の新規性があること (2) 有効性:論文の内容が学術や産業の発展に寄与すること (3) 信頼性:論文の内容が信頼のおけるものであること CINIIに収録されているアイソス誌の記事は4,700件に及ぶ。CINIIに収録されているデータ数(論文、記事、書籍など)は5,100万件というから、その0.01%を占める。(2025/09/27時点) すごいことではある。 |
外資社員様からお便りを頂きました(25.09.30)
おばQさま 「俺にも言わせろ」快刀乱麻のやり取り、楽しく読んでおります。 幸い私は「有益な環境側面」の被害は受けていないので、他人事として楽しめています。 >ISO審査は企業を指導するものと確信している。 この点は、他のISO認証でも、審査員のスタンスとして残っていますね。 マネジメントシステムに関連して、労働問題やセクハラ等の外部通報窓口を指摘してきた審査員がいました。 「即座に認証に関係ないでしょ」と拒否して不適合から消させましたが、ご当人は指摘は「会社を良くすること」だと思い込んでおりました。 「認証の範囲外に手を出す事がNG」という事が判っていない人が時々います。 そもそも認証は、全てのマネジメントシステムを確認できないのだから、実態は抜き取り検査。 だからこそ抜き取り範囲は明確にして、その中はしっかりやる。 その外側は手を出すべきでないのですが、どうもこの辺りを「会社を良くする」と思い込み、未だに誤解をしている審査員がいるような気がします。 >著作者人格権を放棄しないw ひこにゃん事件で、有名になって、契約書に「著作者人格権を行使しない」と書いてくる会社の多い事。 全て削除です。 本来著作者が持つ権利だから、書かなければ問題ない。 似たような恥ずかしい記載では契約書の欄外に「Copyright by 社名」が書いている会社がありました。 契約書は「思想又は感情を創作的に表現したもの」であるとはいえないから、著作物ということはできないのですよね。 |
外資社員様 毎度ありがとうございます。 日々のアクセスを見ると2012年頃がピークで、現在は半減していますが、それでも平日は多い日で450、少なくても300、休日は80くらいはあります。でもお便りはもうないも同然です。外資社員様だけが頼りです。よろしくお願いします。 おっしゃるように、審査員は何か会社に教えていかないとならないとお考えのようですね。すばらしいお話しとか、儲かることなら歓迎ですが、そういう話は聞いたことありません。 外人となるとULの初期(1970年頃)とかISOの初期(1993頃)しか審査を受けたことがありませんが、彼らは<余計なことはしない>というのが記憶にあります。 例えば工場を案内していると、「ここは今回の監査対象品の行程か?」「監査対象品の倉庫か?」と確認します。「そうではない」と答えると、見る必要はないとパスします。日本人の審査員は必ずと言ってよいくらい、「あの工場を見ませんでしたが、何を作っていますか?」と聞きます。審査対象ではないと説明しても見る必要があると言い出して、こちらは予定していないしモノによっては見せられないものもあり、えらく苦労しました。 もっとも慣れてくると、審査対象外の工場を見せて、審査時間を短くするようになりました。とはいえ審査にお金を払っているわけで無駄であることは間違いありません。 著作権とか輸出管理の業務監査を受けたこともありますが、私のような素人には分かりませんね。 それでも海外駐在員は社内を歩き回るにも、外国人と同じく該非判定しないとならないのは覚えました。駐在員がたまに日本に帰って来ると、社内を挨拶回りしますけど大丈夫かなと思っていました。 その逆ですが、ISO認証は技術分野が輸出管理の非該当で指導に行くのも資料送付もフリーパスでした。それだけ技術の価値がないのでしょう。 |
うそ800の目次に戻る
タイムスリップISOの目次に戻る
     |